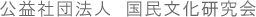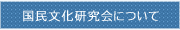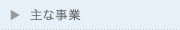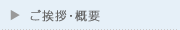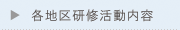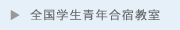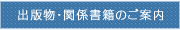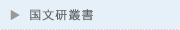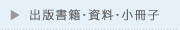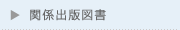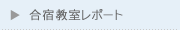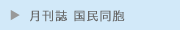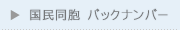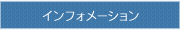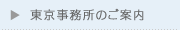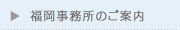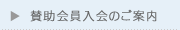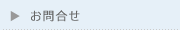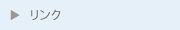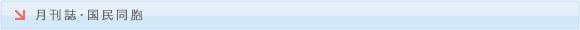
第652号
| 執筆者 | 題名 |
| 平槇 明人 | 怒りを忘れては喰ひ物にされる - 「現代人には、私憤があっても公憤が足りぬ」 - |
| 平成27年にお詠みになったお歌から | |
| 山本 博資 | 平成28年 年頭及び最近ご発表の御製、御歌を拝誦して |
| 澤部 壽孫 | 坂東一男先輩の思ひ出 - 先輩の言行一致ぶりを見て、私は仕事に励んだ - |
| 歌だより抄 新年の挨拶状から |
「思ふに現代人には、私憤は有っても公憤が足りぬ。己の利害や恋愛沙汰には興奮するが、社会の利益・国家利益となると関心が無い」とは、私が勤める亜細亜大学初代学長太田耕造先生が学生たちに示した言葉である。
天晴れ、甘利明経済再生担当相
少し古いが、昨年10月24日付産経新聞に「TPP日米協議舞台裏(上)、響いた甘利氏の怒声」との記事が掲載された。ハワイで7月31日に行はれた環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉を巡る閣僚会合。事前交渉の結果を閣僚会合の場で袖にする米側の不誠実さを、明らかにする甘利明大臣(経済財政政策担当)。「皆さん、今から重要な事をお話しします、聞いて下さい」と切り出し、日米協議の経緯を暴露した。そして声を荒げ「一体、かう成ってゐるのは誰の所為なんだ」と一喝、同時にテーブルを叩く「ダーン!」といふ音が響いたといふ。
アシェイムド 恥づべき! 来栖・野村両大使
この記事を読み、且つフロマン米代表が甘利大臣を睨み付ける写真を見てゐると、一枚の写真を思ひ起した。それは昭和16年11月27日、日米交渉の場で「ハルノート」を突き付けられ、ホワイトハウスでルーズベルト大統領との会談を終へた来栖・野村両大使の写真だ。交渉の成り行きを見守ってゐた米国記者団に取り囲まれた二大使。記者達の表情は強張り真剣そのものである。一方我国の大使達は、間の抜けた笑ひを浮べて居る。
ここは、笑ふ場面ではないはずだ。取り囲む記者達を前に「皆さん、聞いて下さい。これでは戦争になります。大統領は、皆さんの息子を二度と戦場には送らないと約束して当選されました。しかし今回、貴国から提示された条件は、これ迄の交渉を一切無視し、何とか合意に達しようとする我々の努力を踏み躙るものです。我国としては絶対に飲む事の出来ない、謂はば最後通牒に等しい条件を突き付けられました。皆さん、如何思はれますか。これは、我国に敢て最初の一発を撃たせようとの企(たくら)みがあるとしか思はれません」と述べ、交渉の経緯とハルノートの内容を暴露して米国の不誠実さを明らかにし、怒らねばならなかった。
大使はこの後も失態を繰り返す。真珠湾攻撃30分前に最後通牒を手交するとなってゐたが、これをミスった。タイプの仕上げに拘泥する必要は全くなかった。手書でも良かったし、口頭で伝へ後から文書を手交しても良かっただらう。「日本は卑怯な奇襲攻撃を行った」との汚名は未だに晴らされない。国益を著しく損ったのである。
情けない馳浩文部科学相の演説
昨年10月、ユネスコは「南京大虐殺文書」を記憶遺産に登録した。その後のユネスコ総会で、馳浩文部科学相は演説を行った。登録に異議を唱へる絶好の機会であった。しかし大臣は「審査の透明性の向上」を訴へるだけで、共産支那への直接的な言及は避けた。「摩擦を生まぬ様、穏便に申し上げた」との説明通り、極めて不十分な演説であった。
摩擦を生じさせてゐるのは、共産支那ではないか。我が方は断固抗議し、怒髪天を衝くが如き気概を示さねばならなかった。殴られた方が、殴った方に向って、「まあ、まあ、落ち着いて下さい」と言ふ馬鹿がゐるだらうか。誇りと責任感があるなら、猛々しく相手に対さねばならぬ。総会の場で登録撤回を明言せねば、どの国も真剣に受け止めぬであらう。
国益を損ってはならぬ、憤れ!
横田めぐみさんをはじめとする拉致被害者救出もさうである。交渉の場で外務省の職員が北朝鮮の担当者と握手をすることはやむを得ないが、腹の底に憤りがあるのか。自分の娘を誘拐した犯人に向っては、親なら胸倉を掴み「ふざけるな!、何時まで待たせるつもりだ」と怒鳴りつけるだらう。親の怒りをぶつけるのが外務省の役目ではないか。
いささか激語を弄したが、お釈迦様も孔子先生も、人を見て法を説き、相手を見て教へ諭した。我々は、残念ながらジャングルの掟が罷り通る国際社会に生きて行かなければならないのである。怒るべき時には怒らねばならぬ。怒りを忘れては羊でなくとも喰ひ物にされるばかりである。
(亜細亜大学総合企画部)
御製(天皇陛下のお歌)
第66回全国植樹祭(石川県)
父君の蒔(ま)かれし木より作られし鍬を用ひてくろまつを植う
第70回国民体育大会開会式(和歌山県)
作られし鯨もいでて汐を吹く集団演技もて国体開く
第35回全国豊かな海づくり大会(富山県)
深海の水もて育てしひらめの稚魚人らと放つ富山の海に
戦後70年に当たり、北原尾(きたはらお)、千振(ちふり)、大日向(おおひなた)の開拓地を訪(と)ふ
開拓の日々いかばかり難(かた)かりしを面(おも)穏やかに人らの語る
新嘗祭近く
この年もあがたあがたの田の実りもたらさるるをうれしく受くる
皇后陛下御歌
石巻線の全線開通
春風も沿ひて走らむこの朝(あした)女川駅を始発車いでぬ
ペリリュー島訪問
逝(ゆ)きし人の御霊(みたま)かと見つむパラオなる海上を飛ぶ白きアジサシ
YS11より53年を経し今年
国産のジェット機がけふ飛ぶといふこの秋空の青深き中
◇ 平成28年歌会始 お題「人」
御製
戦ひにあまたの人の失せしとふ島緑にて海に横たふ
皇后陛下御歌
夕茜(ゆふあかね)に入りゆく一機若き日の吾(あ)がごとく行く旅人やある
(御製・御歌は宮内庁のホームページによる)
雲一つなく澄みわたった元旦の朝刊に、両陛下が昨平成27年にお詠みになった御製五首および御歌三首が掲載された。国民としての喜びを新たにしつつ拝読した。
天皇陛下の年頭の御感想を併載して、丁寧な解説を加へてゐた産經新聞、東京新聞が特に目についたが、宮内庁が発表したお歌のすべてが全国各紙に掲載されてゐた。年頭ご発表の御製、御歌を拝誦して、拙いながら感想を謹記させていただく。
昨年は戦後70年の節目の年に当り、天皇皇后両陛下は国内外への慰霊の旅を重ねられた。特に、4月のパラオ共和国御訪問は感銘深いものだった。御慰霊とともに意義があったのが、国民の歴史への関心を呼び起したことであらう。
平成21年の御即位20周年の記者会見では、日本の将来で最も心配なことは「次第に過去の歴史が忘れられていくこと」であり、「昭和の歴史には様々な教訓があり、歴史的事実を知って未来に備えることが大切」と述べてをられた。パラオへの御出発前の御言葉のなかでも、「太平洋に浮かぶ美しい島々で、このような悲しい歴史があったことを、私どもは決して忘れてはならないと思います」とお述べになってゐる。この御思ひのままの御慰霊であられたと拝察する。
御訪問は大きく報道され、戦没者に祈りを捧げられる両陛下の御姿を仰ぎ、私達国民は国のために尊い生命を捧げられた父祖たちのことを思ひ起した。8月に発表された安倍首相の「戦後70年談話」も、御言葉を受け止めた内容になってゐたやうに思ふ。
御製
第66回全国植樹祭(石川県)
父君の蒔(ま)かれし木より作られし鍬を用ひてくろまつを植う
全国植樹祭は、昭和25年から始められてゐる。陛下も昭和天皇の御心を受け継がれ、昭和63年の昭和天皇の御名代として御成りになって以降、毎年、御臨席遊ばされてゐる。
天皇皇后両陛下は、5月17日、石川県小松市の木場潟公園で開かれた全国植樹祭に臨まれた。青空のもと、祭典のテーマ「木を活かし 未来へ届ける ふるさとの森」を掲げる会場は、霊峰白山(はくさん)を眺望する場所にある。陛下はクロマツ、ケヤキ、スギの三種を、皇后陛下はアカマツ、ケンロクエンキザクラ、ヤマモミジの三種の苗木を植樹された。また、陛下はアテ、クヌギの種、皇后陛下はヤマザクラ、トチノキの種を御手播きになった。
御製は、御父君・昭和天皇が昭和58年に同県河北郡津幡町の森林公園で開催された第34回全国植樹祭の折、白山市の林業試験場において御手蒔きされたスギの種子が成長し、そのスギで作られた鍬を用ひてクロマツを植ゑられたことをお詠みになってゐる。32年前に御父君が御手植ゑになった杉の木で作られた鍬を手にとられ、杉の真新しい木肌の触感を通して昭和天皇を偲んでをられる御様子を拝するのである。
第70回国民体育大会(和歌山県)
作られし鯨もいでて汐を吹く集団演技もて国体開く
天皇皇后両陛下は、9月25日に和歌山県へ行幸啓になり、26日、和歌山市の紀三井寺公園陸上競技場で開催された「紀の国わかやま国体」に御臨席になった。開会式前の演技で、2千8百余の人たちによって和歌山県の自然風土、歴史、偉人らをアピールした「紀の国のみち」が演じられた。御製は、第1章「森のみち」に続く第2章「海のみち」で会場に引き出された大きな鯨の模型が白煙を上げて汐(しほ)を吹く様を御覧になり、お詠みになったものである。澄み渡る大空のもと、若きらの踊りで躍動する会場の雰囲気が伝はってくると共に陛下のお喜びとあたたかい御眼差しが拝察される。
和歌山県は、捕鯨発祥の地として約400年の歴史があり、捕鯨やイルカ漁は紀南地方の重要産業の一つであった。地域文化の伝承、鯨肉を含む海洋生物資源の保護の必要性を世界に発信してゐる同県の取組みを、応援されてゐるとも拝するのである。
その後、広川町の「稲むらの火の館」を御視察。同館は、安政元年(1854)に紀伊半島を大津波が襲った際、稲の束「稲(いな)叢(むら)」に火を点(つ)けて村人を高台に誘導し、多くの命を救ったとされる濱口五兵衛(悟陵)を記念して建設された。先の開会式前の演技でも濱口悟陵は紹介されてゐた。この「稲むらの火」の逸話は、『小學國語讀本 巻10』の教科書で取りあげられ、数ある教材のなかでも特に深い印象を国民に残したものと言はれてゐる。毎年、地元では津波祭が行はれ、五兵衛の偉業を顕彰して、防災教育訓練の大切さを忘れないやうにしてゐるとのことである。
皇后陛下は、平成11年の御誕生日の記者会の質問に対して、「子供のころ教科書に、確か『稲むらの火』と題し津波の際の避難の様子を描いた物語があり、その後長く記憶に残ったことでしたが、津波であれ、洪水であれ、平常の状態が崩れた時の自然の恐ろしさや、対処の可能性が、学校教育の中で具体的に教えられた一つの例として思い出されます」とお述べになってゐる。
第35回全国豊かな海づくり大会(富山県)
深海の水もて育てしひらめの稚魚人らと放つ富山の海に
「全国豊かな海づくり大会」は、天皇皇后両陛下が地方へお出ましになる三大行幸啓の中で、陛下が皇太子の御時に始められ、大切に続けて来られた御公務である(あとの二つは「全国植樹祭」と「国民体育大会」)。昨年は富山県で10月24日から25日まで開催された。大会は天候にも恵まれ、2日間で延べ3万人を超える人々が来場し、大変盛況のうちに無事終了した。
両陛下は、10月25日、富山湾に面した射水市の多目的ホールで開催された催しに御臨席になり、ヒラメとキジハタの稚魚を御放流になった。翌26日、両陛下は滑川市の「滑川栽培漁業センター」を御視察、飼育中のヒラメやアカムツ(ノドグロ)の稚魚やエゾアワビの稚貝を御見学になった。
富山湾は、蜃気楼、ホタルイカや海底林などから世界的にも珍しい「神秘の海」と称されてゐる。海岸線から急に深くなる地形を有し、表層は日本海を北上する対馬海流と冷たい日本海固有冷水(深層水)が層をなしてゐる。そこへ立山連峰に源を発する河川・地下水が流れ込み、新鮮な酸素と栄養を供給し、数百種の魚が生息する「天然のいけす」と呼ばれる好漁場となってゐる。一方では、漁業経営が厳しくなるなかで、資源管理型漁業やつくり育てる漁業の一層の推進などが、大会の基本方針に取りあげられ実施されてゐる。
御製は、富山湾の深層水で飼育されたヒラメの稚魚を、母なる海にて成長することを願ひ御放流になったことを詠まれてゐる。県民挙げての「豊かな海づくり」の取組みに、陛下も同じお気持ちで参加して御推進されてゐると拝察するのである。
戦後70年に当たり、北原尾(きたはらお)、千振(ちふり)、大日向(おおひなた)の開拓地を訪(と)ふ
開拓の日々いかばかり難(かた)かりしを面(おも)穏やかに人らの語る
詞書に記されたやうに平成27年が戦争終結から70年の節目に当り、外地から引揚げてきた人々の開拓地への御訪問を強く望まれ、6月から8月にかけての御訪問となった。
敗戦を境に身一つで海外から引き揚げてきた人たちは、何処で、どのやうな仕事をし、どのやうな思ひで生きてきたのか、その苦難に満ちた歩みを忘れてはならないとの強い大御心を拝し奉るのである。
6月17日、両陛下は宮城県の蔵王町の北原尾を御訪問された。山形県のみの私的な御日程のなかで、強い希望で立ち寄られることになった。終戦後、パラオから戻ってきた人たちは、パラオを忘れないとの想ひから、「北のパラオ」の意味を込め、地名を「北原尾」と命名して入植した。入植者は、一面に広がる森林を手で掘り起し切り墾(ひら)いて、現今「酪農の北原尾」と呼ばれるまでに開拓した。激戦地のパラオから引揚げてきた人々に、ずっと御心を御寄せになってゐる御様子が拝察される。
7月20日には、両陛下は福島県境に近い栃木県那須町豊原(とよはら)丙(へい)の千振地区を訪ねられた。千振地区は那須連山の山麓に広がる4、5百メートルの準高冷地で、戦後に満州から引揚げてきた人々によって、強酸性土壌で流水の便が皆無に等しい不毛の地が沃野に開拓され、現在は酪農中心の農業が営まれてゐる。千振開拓地を御訪問になった両陛下は、入植者や家族ら七人と懇談された。戦後60年に当る平成17年にも同開拓地を御訪問になってゐる。
ついで8月20日、両陛下は長野県軽井沢町の大日向地区に足を運ばれた。長野県の旧大日向村は戦前、村を二分して満州に移住し「満州大日向村」をつくった。戦後、引揚げてきた人たちは、浅間山麓に入植し、再び「大日向」と名付けて開拓を進め、酪農、高原野菜の栽培が出来るまでに整備された。大日向開拓地区を御訪問の両陛下は、開拓記念館で入植当時に使用した鍬や鎌など御観覧なった後、70、80歳代の入植者8人と懇談された。両陛下は、皇太子・同妃の御時から度々、この地を御訪問になってゐる。
御製は、各地区で入植した人たちと懇談され、その話をお聞きになられたときのことを詠まれたものである。開拓の仕事がどれほど過酷で苦難に満ちたものであったか想像に絶する日々であったにもかかはらず、入植者たちはその労苦を乗り越え、「面穏やかに」語る。両陛下は静かにそれに耳を傾けてをられる。過去の苦難の日々を想ひつつも、両陛下と入植者達の心の通ひ合ふ和やかな場面が髣髴とする御作である。
新嘗祭近く
この年もあがたあがたの田の実りもたらさるるをうれしく受くる
新嘗祭(にひなめさい)は、毎年11月23日に宮中三殿に付属した神嘉殿で天皇が御親祭される宮中祭祀のひとつで、五穀豊穣の収穫祭に当る。最も重要な祭祀とされてゐる。
新嘗の「新」は新穀(初穂)を、「嘗」は御馳走を意味し、天皇陛下が宮中で初穂を天照大御神はじめ天神地祇に御供へされ、御自らも初穂を召しあがり、神様の恵みによって初穂を得たことを感謝される御祭である。神嘗祭と同じく伊勢神宮には勅使が遣はされる。
新嘗祭においては、皇居内の水田で刈り取られた新米や、粟などと共に、各都道府県から奉納された皇室献上米が神々に御供へされる。毎年この時期に両陛下は、都道府県の関係者と献上農家にお会ひになって感謝の御気持をお伝へになる。
御製は、神々に本年の「田の実り」を奉告されると共に、各「県(あがた)」よりの献上米を「うれしく受くる」と率直に御喜びの御気持をお詠みになってゐる。献上農家の人々が米作りに精根をこめる労(いたつき)にもお心を寄せられた御作と拝察するのである。「タ」行の音のしらべが心地よく沁みる。
皇后陛下御歌
石巻線の全線開通
春風も沿ひて走らむこの朝(あした)女川(をな がは)駅を始発車いでぬ
石巻線(いしのまきせん)は、東日本大震災で被災し、一部区間の不通が続いてゐたが、3月21日に、女川駅―浦(うら)宿(しゆく)駅間の復旧により四年ぶりに全線開通した。被災したJR在来線のうちで最初の全線再開であった。駅舎も新しくなった女川駅周辺の復興を宣言する「まちびらき」に合せての開通で、その始発列車は女川駅から出発し、新たな一歩を踏み出した。
両陛下は、その直前の3月13日、東日本大震災後四回目の宮城県入りを果され、15日にかけて岩沼、名取、東松島、石巻市の被災地に足を運ばれ復興状況を見て回られた。石巻市は初の御訪問となった。
皇后陛下は、石巻線沿線の復興状況を御視察になってをられたので、開通の知らせを格別な御思ひでお聞きになられたと拝察する。力強く復興しつつある町の情景が目に浮ぶ。沿岸部の鉄路再生が進み、復興のシンボル「始発車」に「春風も沿ひて」励まし応援してゐるやうな様子を思ふと共に、御自身を春風に託され一緒に走りたいとの御気持が拝察されるが如き御歌である。
ペリリュー島訪問
逝(ゆ)きし人の御霊(み たま)かと見つむパラオなる海上を飛ぶ白きアジサシ
天皇皇后両陛下は、4月8、9日の2日間、南太平洋のパラオ共和国を御訪問になった。天皇陛下が10数年来、願ひ続けられたパラオへの御慰霊の旅である。日本の委任統治下のパラオでは、一万余の日本人将兵が散華してゐる。両陛下は、南部の要衝ぺリリュー島で、戦死者の霊に祈りを捧げられた。
皇后陛下は、10月20日の御誕生日に際しての宮内記者会の質問に対して、パラオへの御慰霊の旅に触れられ、「かつてサイパン島のスーサイド・クリフに立った時、三羽の白いアジサシがすぐ目の前の海上をゆっくりと渡る姿に息を呑んだことでしたが、この度も海上保安庁の船、『あきつしま』からヘリコプターでペリリュー島に向かう途中、眼下に、その時と同じ美しい鳥の姿を認め、亡くなった方々の御霊に接するようで胸が一杯になりました」と文書で回答されてゐる。
まさにこの情景をお詠みになった御歌である。アジサシは、カモメ科に分類され、鳩と同じくらいの大きさで海岸や河川の砂浜に巣をつくる。古来、蛍を身体から遊離した魂に見立てる和歌も多いが、このアジサシを英霊と受け止められ、御心を注ぎ見入られてゐる御様子を拝察するのである。
YS11より53年を経し今年
国産のジェット機がけふ飛ぶといふこの秋空の青深き中
戦後、わが国は驚異的な復興を遂げ、各種の高品質の工業製品を生産し世界に冠たる工業国になったが、航空機産業だけは育たなかった。わが国の航空機開発技術は、戦前戦中を含め世界のトップレベルにあったが、戦後、GHQ(占領軍総司令部)は航空機産業全般を厳しく制限した。米国を中心とした戦勝国は、わが国の航空機開発の技術力を恐れたのであり、制約は現在も未だ続いてゐる。このやうな状況下においても航空機関連メーカーは、部品製造や素材の開発・供給を細々と続けて、技術力を大いに磨き蓄へてきた。そして、先づ実を結んだのが、昭和37年8月に初飛行を行った近中距離用の双発式プロペラ旅客機「YS11」であった。詞書にあるやうに、それから53年を経た昨平成27年11月11日、遂に国産初のジェット旅客機MRJ(ミツビシ・リージョナル・ジェット)が試験飛行に成功した。最先端技術を取り入れ機体の軽量化、優れた環境適合性と運航経済性を兼ね備へた国民期待の航空機の誕生である。
MRJが秋の青く澄み渡った大空に飛ぶ様に思ひを馳せられてお詠みになった御歌である。初飛行成功の深い御慶びの御気持を拝察する。
天皇陛下は、82歳の御誕生日に際しての記者会見において「日本製のジェット旅客機が完成し、試験飛行が行われたこともうれしいことでした」とお述べになった。両陛下ともに「日の丸」航空機の前途を祝福され、安全運航と飛躍を願ってをられるものと畏くも拝するのである。
歌会始 お題「人」
新年恒例の「歌会始の儀」が、1月14日、皇居正殿「松の間」において行はれた。
御製
戦ひにあまたの人の失せしとふ島緑にて海に横たふ
パラオ御訪問の両陛下は、4月9日、日本政府がペリリュー島最南端に建立した、島の岩を埋め込んで作られた「西太平洋戦没者の碑」に、持参された白菊を供花され鎮魂の御祈りをささげられた。さらに、碑の脇にお立ちになり、碑の後方に広がる海上に浮ぶ緑濃きアンガウル島に向って暫し黙礼された。同島でも、約1,100人の日本守備隊が戦死してゐる。御製はこの時のことをお詠みになってゐる。「とふ」は「と言ふ」の謂。
この拝礼は、陛下の御意向で急遽予定に入れられたとのことである。今回のパラオ御訪問でも、現地に出向くことが追悼と慰霊の原点であることを、両陛下は言外にお示しになってゐるやうに思はれるのである。
皇后陛下御歌
夕(ゆふ)茜(あかね)に入りゆく一機若き日の吾(あ)がごとく行く旅人やある
夕方の茜色に染まる空の方角に飛び進んでいく飛行機をご覧になりながら、御成婚前年の昭和33年、御一人で欧米各国を旅されたことを思ひ出され、自分と同じやうな旅する若者が乗ってゐるのではと想像された御歌。
遥かに遠い異国への一人旅から多くのことを見聞された御経験を踏まへ、希望や夢を抱いて進んで行く若者への期待と活躍を願はれてゐるものと拝察されるのである。
○
御製は平成25年まで植樹祭、国民体育大会、豊かな海づくり大会の三大行幸啓の三首を含む八首であったが、26年は陛下の御年齢を考慮したとの説明で六首になった。残念なことに、さらに27年は5首になった。
年初にお示しになる御製は国民の心の指針となり活力の源泉となるものである。漸減しないやうに宮内庁の再考を強くお願ひする。
宮内庁のホームページ、『祖国と青年』誌および「神社新報」紙を参照させていただきました。厚く御礼申し上げます。
(元川崎重工業(株))
本会元常務理事、坂東一男先輩には、昨年9月10日逝去。享年数へ79であった。
坂東先輩は父君・嘉市さんと母君・イツさんの長男として昭和12年5月20日に旅順でお生れになった。生後すぐ亡くなった姉君、三人の妹君および三人の弟君の七人兄妹弟であった。父君は法務局にお勤めで、母上は小学校の先生で校長を務められた。
昭和20年8月9日、日ソ中立条約を破ったソ連軍が侵入してきたのを見て、30分で旅順を退去し母君に連れられ日本に向ったといふ。引揚げ後は父上の実家のあった宮崎で成長、宮崎県立大宮高等学校から長崎大学経済学部に進まれた。昭和36年に御卒業、アサヒビール(株)に入社。営業担当として、東京支店、九州支店などに勤務し、昭和55年に仙台支店次長、昭和59年には新潟支店長を拝命されてゐる。
昭和63年、本社の飲料営業部長となり、アサヒ飲料(株)の設立に関り、平成2年、アサヒ飲料(株)の発足と同時に同社の取締役営業部長、平成5年に常務取締役近畿圏支社長に就任された。平成7年の阪神淡路大震災の際には会社と御得意先の復興に意を注がれ、その働きぶりは今でも社内で語り継がれてゐるといふ。その後、平成11年から専務取締役首都圏支社長を務め、平成14年3月に定年退職された。
昭和40年に御結婚、お優しい奥様・厚子様との間に7人のお子さん(裕君、文子さん、恵子さん、陽子さん、幸子さん、直子さん、剛君)に恵まれ、アサヒグループで一番の子沢山であったといふ。小田村寅二郎初代理事長から5人以上の子宝に恵まれた者として「金杯」を授与されたのも坂東先輩お一人である。8年前の末っ子・剛くん(早稲田大学在学中)の急逝は、まさに痛恨の極みであられたと御胸中をお察しするばかりであった。
○
昭和50年から長らく本会の理事(のち常務理事)の大役を果され、平成3年8月の第30回合宿教室(厚木)では導入講義を担当、演題は「楽しき哉!敷島の道」であった。また、本会監事の故星野貢先輩((株)中央塩ビ製作所会長)の肝煎りで平成13年8月に刊行された「古事記朗読CD」8巻の販売を引き受け、1,000部(単価16,800円)を完売されたのは今でも会員の間で語り草となってゐる(このCDの原盤は昭和53年に故夜久正雄先生がテープに吹き込んだもの)。平成17年には一時期、事務局長をお務めになった。
本会との縁は、三菱重工業(株)長崎支店に勤務されてゐた同窓(旧制長崎高商卒)の小縣一也先輩(元本会理事)に誘はれて、昭和33年夏の第3回合宿教室(阿蘇)に参加されたことからであった。私は長崎大学1年の昭和35年に初めて合宿教室に参加したが、それが機縁となって半年ほどの間ではあったが、小縣一也先輩のお宅にしばしば連れて行かれた思ひ出がある。坂東先輩が始められた長崎大学の勉強会「信和会」は私、合原俊光君および内田英賢君と順に引き継がれた。
昭和37年春、小田村寅二郎先生の呼び掛けで営まれた東京青山での幹部学生合宿に参加のため上京した時は、合原俊光君とともにアサヒビール阿佐ヶ谷寮(杉並区)に泊めて頂いたが、関東地区の会員たちも葉山や箱根のアサヒビール寮を何度も使はせたもらったといふことだ。
○
坂東先輩は、皇室を尊ぶお心が篤く、折あるごとに短歌を詠まれ、私が編集発刊してゐた「澤部通信」に度々投稿された。短歌を詠むことによって、さらに心を鍛へ生き方を整へられたものと思はれる。その言行一致ぶりは、私達実業人の見本であり、先輩の背中を見て私も商社の勤務に励んで来た。アサヒ飲料(株)に入社した愚息が身近な上司に、「坂東一男さんはどのやうな方でしたか」と尋ねたところ、「朝礼で全社員を前にして明治天皇御製を朗々と拝誦されるお人であった」とのことで、朝礼にはいつも感動したと答へたさうである。〝飲んだビールが5万本〟と豪語され、得意先の開拓に尽力された。「アサヒは飲むもので読むものではない」との辛辣な朝日新聞批判の名言も残された。
我が身を忘れて営業活動に邁進、その結果、体調を損はれ、平成24年3月から、渋谷区広尾の日赤病院で人工透析を余儀なくされることになった。最初は火・木・土が透析日であったが、「東京中條塾」(代表世話人)や「国策研究会」(顧問)の、志の高い青年達の育成のため勉強会が土・日の開催で重複するため月・水・金となったといふ。透析が始まったら何があっても休めない。初め一時間だった透析時間は次第に長くなり最後は五時間を要した。日赤病院からの帰途、しばしば渋谷区東の本会事務所に立ち寄られた。いつも、透析後のお疲れの見えるお顔で入って来られるが、折々の時局を憂ひて大きな声で語られる内に、次第に生気みなぎる御顔に一変して、お帰りになるのには驚かされた。その度に我々も元気を頂戴したのである。
幾度も合併症で危機に直面されながら驚嘆すべき精神力で乗り越えられ、昨年3月末、箱根で開催された一泊の関東地区会員の合宿にも参加、20余名を前に、阪神淡路大震災の折のアサヒ飲料(株)近畿圏支社長としての奮闘ぶりを力強く語ってくださった。しかし、悲しいことに、その半年後の昨年9月10日夕刻、つひに帰らぬ人となられた。病床から御殿場の合宿教室最終日(9月4日)に御寄せになったお歌は「学生の数は少なくなりたれど思ひの深さに合宿続く」であった。
思ひ出は尽ないが、坂東先輩が長崎大学経済学部の同窓会誌に、お亡くなりになる直前に投稿された絶筆を最後に掲げたい。紙面の都合で、前半のみであるが、先輩のお心を偲びたいと思ふ。
『瓊林友の会』第70号 戦後70年に思ふ 学部八回 坂東一男
昭和20年8月15日は日本が初めて外国との戦争に敗れた日である。従ってこの日以降が戦後となり、今年の8月15日で丁度戦後70年となる。昭和から平成へとつづくこの70年の歩みを、昭和天皇の御製と今上陛下の御製を中心に、私自身の来し方も含め、振り返ってみる。
昭和20年8月15日正午、昭和天皇はラジオを通し(玉音放送)「…堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ビ難キヲを忍ビ以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス」と戦争の終結を告げられ、国家の分裂もなく、戦後は始まった。私は数へ年九歳であった。大学時代に御製にふれて以来、社会人となって現在まで折々に御製にふれて励まされ苦難を乗り切って生きて来たと言へる。
昭和天皇御製 (昭和20年)
爆撃にたふれゆく民の上をおもひいくさとめけり身はいかならむとも
この御製は、終戦時に昭和天皇がお詠みになった四首の冒頭の御歌である。「爆撃にたふれゆく民の上をおもひ」と国民への溢れる思ひを述べられ、「身はいかならむとも」と結ばれた。五七五七七の音調を整へるのではなく心に思ふことをそのまま率直に詠んでをられるのでかへって心を打たれる。
この御製に続く三首の歌は以下の通りである。
身はいかになるともいくさとどめけりただたふれゆく民をおもひて
国がらをただ守らんといばら道すすみゆくともいくさとめけり
外国(とつくに)と離れ小島(をじま)にのこる民のうへやすかれとただいのるなり
伊勢神宮に参拝して(昭和29年)
伊勢の宮に詣づる人の日にましてあとをたたぬがうれしかりけり(昭和45年)
ななそぢを迎へたりけるこの朝も祈るはただに国のたひらぎ
「迎へたりけるこの朝も」をただ単に「迎へし」あるいは「迎へたる」ではなく「迎へたりける」との御表現に70歳をお迎へになった深い御感動が偲ばれる。さらに「この朝も」の「も」に日々の御祈りを暗示し給ひ、「祈るはただに国のたひらぎ」と強く結ばれてゐる。昭和45年は33歳であった私にも衝撃的な事件が起きた。尊敬してゐた三島由紀夫氏が市ヶ谷の自衛隊にて憲法改正を訴へて割腹自殺し、大阪万博で上げ潮ムードの日本国に衝撃を与へた。当時の拙詠が無いのが残念である。
(昭和49年)
大統領は冬晴のあしたに立ちましぬむつみかはせしいく日(にち)を経(へ)て
現行憲法では、天皇陛下はロボットのやうに見られやすいが、その天皇様が国際親善の為にどれほどお尽しになってをられるかを我々が知る事の出来る御製である。戦後初めて米国のフォード大統領が昭和49年秋に訪日し、天皇陛下にお会ひして、深く感動して帰国されたことは、当時の大統領談話として報道され、今も記憶に鮮やかである。難しい言葉は一言もない。
初句で「大統領は」と字余りながらずばり述べられ、「冬晴れのあしたに」とこれも字余りである。第三句の「立ちましぬ」で敬語はどっしりした区切れとなってゐる。下の句に「むつみかはせし幾日(いく にち)を経(へ)て」と述べられ、倒置法になってゐるが、ひと言ひと言に真心を込めて語られる陛下の誠実なお人柄そのものが表現された名歌であると拝される。このお心が外国の元首方に通じない筈がない。
「澤部通信」に掲載されてゐる当時の私の拙詠は「新しき年のほぎごと言ひ交す食卓囲み吾子らと共に」、「カルタとる子らの声々響きけり年の初めの陽光(ひかり)をあびて」である。忙しい中に「澤部通信」に投稿することが支へであった。
─後略─
(元日商岩井(株)エネルギー本部 副本部長)
お題「人」に寄せて
佐世保市 朝永 清之
引揚げ後の消息しれぬ人々は戦後をいかに暮し来つらむ(北朝鮮から)
七十年の歳月遠くなりたれど共に過しし人ら懐かし
柏市 澤部 壽
空青く水清らなる海の辺に父母眠る里の人らと孫
八千代市 山本 博資
人びとの努力実りてふるさとの炭ほる設備世界遺産に
府中市 磯貝 保博
先人の言葉たどり教へをば学びゆきたし若き友らと
小田原市 岩越 豊雄
み日光(ひかり)のありがたきかな隔てなくおのもおのもの人を直(ただ)さす
横浜市 山内 健生
人あまた寄りて賑ふ故郷の祭礼(まつり)を想ふ齢(よはひ)数へつつ
小矢部市 岸本 弘
両陛下の御来県(10月)
十三夜の月皓皓と照る芝にあまたの人らとお出ましを待つ
川越市 奥冨 修一
夕暮れて開きゆくかな真白くもあやしき色の月下美人は
鎌ヶ谷市 向後 廣道
つはものの眠れるペリリュー島人は歌ひくれたり日本の歌
宮若市 小野 吉宣
合宿教室
人生をよりよく生きよと輪になりて語り合ひけり学生たちと
福岡市 山口 秀範
ミャンマー国ヤンゴン郊外の「大東亜戦争陣没英霊之碑」前で
激戦地インパールに近きこの町の日本人墓地今ぞ詣づる
南国の大地に屍(かばね)さらしたる人らのありて国護られぬ
熊本県益城町 折田 豊生
小柳陽太郎先生を偲び奉る
人々とともに学ぶが学問と諭したまひし師の君を憶ふ
世田ヶ谷区 梶村 昇
九十を一つ越えたり今年また健やかなれと願ふこのごろ
町田市 三宅 章文
菜園折々
寒中の畑耕す吾近く百舌鳥の飛び来て長き尾を振る
朝の霧いつしか晴れて我が畑の野菜露けく緑輝く
久留米市 合原 俊光
風ぬるみ花咲きそめし宮園に春の訪れ思ふ朝かも(久留米水天宮、3月)
白銀の雪をいただく岩木山北の大地は輝きて見ゆ(青森行きの機中、5月)
浦安市 小林 功
幸くわれ昭和の御代ゆ平成と時の移ろひ側衛(そくえい)にありて
神奈川県真鶴町 稲津 利比古
橘曙覧「独楽吟」にあやかりて
たのしみはパンの香りのただよひて焼き器の蓋を開けるその時
たのしみは古(いにしへ)の書(ふみ)友と紐解きて古人の心を偲びあふ時(五首の内)
下関市 寶邉 幸盛
初孫の舜(しゅん)の瞳や初日の出
さいたま市 井原 稔
昨春(穀雨の候)見沼田園にて
暖かき光川面に満ち満ちて青葉若葉の季節(とき)となりぬる
緑なす大地明るき陽を浴びて生命(いのち)と生命輝きをれり
福岡市 小柳 左門
新しき年の朝(あした)のうららなる空に浮びく父の面影(おもかげ)
横浜市 松井 嘉和
(11月、ポーランドの日本学学者、コタンスキ教授の墓に参る)
黄金(こがね)色(いろ)秋の名残の葉はあれどワルシャワの墓地吹く風寒し
柳井市 寶邉 矢太郎
映画「海難1890」
荒狂ふ海に沈みしエルトゥールル号あまた犠牲者島に流れ来
村人らこぞりて息ある人救へと必死の看病たたかひにけり
ひなの地の名も無き人ら貧しかるに食をほどこし衣も与へたり
大和市 松本 洋治
地平線真つ赤に空をそめあげて初島沖に日はのぼりくる
岡崎市 松藤 力
日台交流「霧社に桜を」ツアー
恩讐の歴史遺すも仁愛郷集ひ祈りて桜の園と
由利本荘市 須田 清文
戦後70年、亡き父を偲ぶ
身のかぎり心の心かぎりつくされしいくさのことども語りし父かな
次々と命おそひしあまたなる事にまむかひしますらをわが父
今あるは命をかけて戦ひし父ありてこそとひたに偲びぬ
藤沢市 工藤 可哉
映画「海難1890」を観て
外国(とつくに)のみ祖(おや)助けし我が父祖(ふそ)のまごころ功(いさを)心に満つる
埼玉県嵐山町 服部 朋秋
初詣
みひかりを浴びて輝くおほやしま榊ささげて弥栄いのる
率土(そつと)の浜(ひん)くまなく照らすひさかたの光いや澄む皇国(すめぐに)の春
薩摩川内市 小田 正三
卒業の祝ひに貰ひし万年筆を今も使ひぬ深き縁(えにし)に
熊本大学「信和会」昭和52年卒)
茅ヶ崎市 北濱 道
旧臘、足柄峠を訪ふ
道ゆけば天に向ひて真つ直ぐに伸びたる杉の木立美し
峠にて「あづまはや」と嘆かしし倭建命偲びぬ
編集後記
年頭ご発表の御製御歌を「国民としての喜びを新たにしつつ拝読した」と謹解の筆者は先づ記す。まさに「言霊の幸(さきは)ふ君民一和の国」の民が知る喜びである。ご精読ください。
(山内)