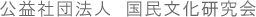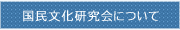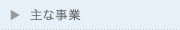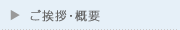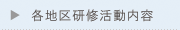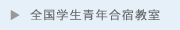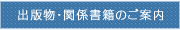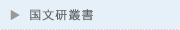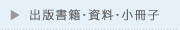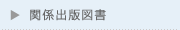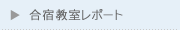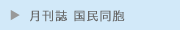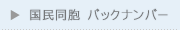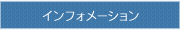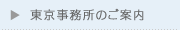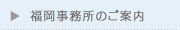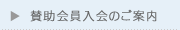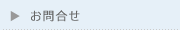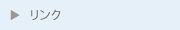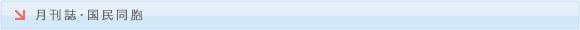
第630号
| 執筆者 | 題名 |
| 前理事長 上村 和男 |
今後とも変らぬ御支援御協力を - 理事長退任に当って感謝しつつ思ふこと - |
| 小柳 左門 | 民主主義を越えるもの - ゲティスバーグ演説、憲法17条、五箇条の御誓文 - |
| 稲津 利比古 | 明治憲法に殉じた清水澄博士 - 日本国民へ託された悲願 - |
| 稲田 朋美 | 私が政治家となった原点 (「南京裁判」展転社を支援する会 会報第四号-平成25年11月-から) |
| 新刊紹介 『マジック消しゴム 時代旅行』 石川 一郎太(文芸社) |
昭和29年8月、八代市郊外の春光寺での合宿に参加したのが、国文研との関りを持つ切っ掛けとなった。60年も前のことである。鹿児島から参加したのは川井修治先生(当時、鹿児島大学文理学部講師。のち国文研副理事長、鹿大教授、同名誉教授)、医師の小川幸男先輩、そして鹿大1年生の私の三人であった。講和条約の発効(独立)から2年後であり、八代にはのちに市の助役をお務めになる加藤敏治さんがをられた。
昭和18年、東条内閣の忌避に触れて日本学生協会と精神科学研究所が解散を命ぜられてから10年余、雌伏の時期を経て、同志たちが祖国の再建に向け再び歩み始めた頃であった。
当時の国情は、日教組等の左翼勢力が強く、共産革命による国家再建が叫ばれてゐた。さうした中にあって、春光寺合宿では政治イデオロギーの問題よりも、精神的思想的な事柄に時間が費やされた。政治偏向の日教組教育を受けた学生が果して正しい国家観を持ち得るのかといふことなどが、夜を徹して議論された。
国民文化研究会の発足は昭和31年1月であり、その年の8月には第1回の合宿教室が霧島で開催された。当時の名称は「全九州学生青年霧島合同合宿」であった。この時の写真を見ると、小田村寅二郎、夜久正雄、瀬上安正、寶邉正久、加藤敏治、末次祐司、小柳陽太郎、山田輝彦、小縣一也、名越二荒之助ほかの諸先生諸先輩のお顔がある。40歳前後のお歳で今思へばお若かった。その中に私も入ってゐる。
大学を卒業後、東京の会社に就職したことで、関東地区にお住ひの先輩方との新たな交流が始まった。合宿教室参加の後輩会員や学生たちとも読書会や小合宿で付き合ふやうになった。本格的な経済復興の時期と重なって業務は多忙だったが、国際政治学者・若泉敬さん(当時、防衛庁防衛研究所。のちに京都産業大学教授)らの勉強会にも顔を出して、「安全保障や国際政治」について話し合った。さうした中で現憲法の改正なくして国家再建は覚束ないとの認識を改めて強くしたのであった。
昭和40年頃から、仕事で各地に出向くことが多くなった。さうした折、仕事が一段落した後、その地に居を構へたり勤めてゐる国文研の仲間(多くは後輩たちだったが)に会って、近況を尋ねて絆を確かめ合った。
夏の合宿教室は昨年の厚木市での開催で58回を数へたが、この間、数回仕事の関係で参加出来ないことがあった。業務が海外に広がって、東南アジアへの出張と合宿時期が重なったことが何度かあったからである。国内にゐる時の夏は「合宿教室」であった。小田村寅二郎理事長からは会社によく電話をもらった。ことに毎年、合宿開催が近づく6月7月頃になると日に何度も電話が掛かって来た。すぐに受話器を取れないこともあったが、先生の学生指導に懸ける情熱は、今思ひ返しても凄かった。
図らずも平成11年5月、小田村先生の後を襲いで理事長の大役を担って15年、賛助者の皆様を初め国文研会員の大きなお力添への御蔭で、毎夏の合宿教室その他の諸事業が滞りなく展開出来たことは本当に有難いことであった。欲を言へば合宿参加の学生の漸減を克服して漸増の方向に転じたかったのだが、何はともあれ、皆様の御理解と御協力に感謝するばかりである。
前述の第1回合宿教室、即ち「全九州学生青年霧島合同合宿」の報告集のタイトルは『昏迷の時代に指標を求めて』といふものだった。あれから60年近くなる。しかし、今でも残念ながら同質同様の「昏迷の時代」がなほ続いてゐる。
明治憲法の改正条項に拠るといふ擬制によって「押し付けられた憲法」が今も国政の根本に据ゑられたままだ。その矛盾は年々覆ひがたくなってゐて、国家再建の方途は明確であるのにその歩みは遅々としてゐる。かうした中で、次代を担ふ有為なる学生青年の育成を念願とする本会の任務はいよいよ重いものがある。今林賢郁新理事長の下でさらなる充実が計られるものと期待してゐる。今後とも本会に変らぬ御支援御協力をお願ひしつつ退任の御挨拶とさせていただく。有難うございました。
米国のゲティスバーグで行はれたリンカーン大統領の演説(1863年)の一節、「国民の国民による国民のための政治」は、しばしば民主主義の精神をあらはす言葉として代表されます。かつて私も ゲティスバーグを訪れましたが、南北戦争によって多くの兵士の命が失はれたこの地には、各州の兵士を顕彰する像が立ち並んでゐました。アメリカ合衆国国民の悲しみと新たな決意を胸に、リンカーンの演説はなされたことと思はれます。
米国流の民主主義が日本に本格的に上陸したのは、我が国の敗戦に続く占領の時でした。私が子供のころにはラジオでよく民主主義といふ言葉が宣伝され、学校でも、戦争前には我が国に民主主義はなかったものがアメリカによってもたらされたと教へられました。だがそれは正しいことだったのでせうか。
一体、民主主義とは何か。あの独裁国家北朝鮮でさへ、「朝鮮民主主義人民共和国」と呼称してゐるではないですか。
◇
今の我が国で民主主義を示す現実的な制度として、多数決による決議や国民の普通選挙などがあります。成人式では、選挙で投票することが国民の政治参加であり、それは国民の権利であると喧伝されてゐます。
だが現在、若者を始めとして多くの国民は、選挙に対する言ひ知れぬ不信感を抱いてゐます。選挙戦を最大限に利用したのが民主党による政権交代でした。衆議院選挙を前にマニフェストを掲げましたが、それぞれの内容には過半の国民が納得しなかったにも関らず、選挙に勝ち政権をとったといふ理由でそれらを推し進め、結局破綻したのが鳩山小沢政権でした。結果として国民の大いなる反発を招いたにも関らず、党内だけの確執で再び台頭しようとしてゐます。これが民主主義といふものなのでせうか。さうであるならば、民主主義の制度とはなんと不安定で実のないものであることでせう。
◇
リンカーンが訴へたのはそんなものではなく、アメリカを自由平等の国家として存続するために、国民一人一人が身を捧げるべきことを、南北戦争で亡くなった人々の前で誓ったものなのです。
ワシントンのアーリントン国立墓地には南北戦争以来の戦争で亡くなった兵士の幾万もの墓が並んでゐますが、そこには故ケネディ大統領の就任演説における有名な一節、
| 「国が諸君に何をなすことできるかを問ふのではなく、諸君が国のために何をなすことができるかを問ひ給へ」 |
を刻む碑があり、常に衛兵が守ってゐます。
この二人の大統領が訴へたものは、国のために奉仕することの貴さでした。それは多民族をかかへるアメリカ合衆国を成り立たせてゆく、民主主義の基本精神でもありませう。
◇
翻って我が日本ではどうでせうか。
国や公のために尽すといふ精神はますます希薄になったゐないか。自分たちの目先の利得に目を奪はれ、政治を利用してゐるのが大半ではないか。内治および外交において国全体の方向を見定め、国家百年の計を図ることに心を砕いてゐる人がどれだけゐるのでせうか。
明治維新といふ激動の時代を迎へて、明治天皇が国民とともに誓はれたのは、「広く会議を興し万機公論に決すべし」を始めとする五箇条の御誓文でした。どんな事でも公の人々の論を尽して決すべきである、といふ言葉に託された第一条の精神は、第二条の「上下心を一にして、盛んに経綸(国を治め民を救ふこと)を行ふべし」といふ利他協力の心に支へられてゐます。さらに第三条には、官にある人から庶民に至るまで、各々の志を遂げられるやうに、国民の心をして失望させないように、との広い叡慮が示されてをり、これらの御誓文に込められものは民主主義の基本に通じるものでした。
◇
さらに明治維新から遡ることほぼ1200年、聖徳太子が定めた憲法17条の第17条には、「それ事は独り断ずべからず、必ず衆と與に論ずべし」とあり、事を決する時、とくに重要なことについては必ず人々とともに論じなさい、と述べられてゐることに驚きを覚えます。
(次頁四段に続く)
五箇条の御誓文
(慶応4年・明治元年(1868)3月14日、明治天皇が京都御所の紫宸殿にて、公卿・諸侯(諸大名)を率ゐて天地神明に誓はれる)
一 広く会議を興し万機公論に決すべし
一 上下心を一にして盛にけいりん経綸を行ふべし
一 官武一途庶民に至る迄各其志を遂げ人心をして倦まざらしめん事を要す
一 旧来の陋習を破り天地の公道に基くべし
一 智識を世界に求め大に皇基を振起すべし
我が国未曾有の変革を為んとし、朕躬を以て衆に先んじ、天地神明に誓ひ、大に斯国是を定め、万民保全の道を立んとす。衆亦此旨趣に基き、協心努力せよ。
(この御誓文に対して、有栖川宮熾仁親王が、左記の奉答文を奏せられ、三条実美総裁以下の公卿諸侯が署名して奉った。)
奉答文
勅意宏遠、誠に以て感銘に堪へず。今日の急務、永世之基礎、此他に出べからず。臣等謹て叡旨を奉戴し、死を誓ひ、黽勉事に従ひ、冀くは以て宸襟を安じ奉らん。
(大意)天皇のご意志は遠大であり、誠に感銘に堪へません。今日急務である国作りと国家永久の基礎は、これに拠る他はありません。我ら臣下は謹んで天皇の御意向を戴いて、死を誓って、勤勉に奉仕して、御心を安じ奉らんと願ふのみであります。
※五箇条の御誓文は、その後の新政府の組織作り、民撰議院設立(国会開設)の建白、自由民権運動の拠りどころなったばかりか、昭和21年元旦の「新日本建設ニ関スル詔書」の冒頭にも掲げられてゐて、戦後政治の原点にも据ゑられてゐます。
憲法十七条(抄)
(推古天皇12年(604)4月3日、太子親ら憲法を作りたまふ)
一に曰く、和を以て貴しと為し、忤ふこと無きを宗と為す。人皆党有り、亦達れる者少なし。是を以て、或は君父に順はず、乍隣里に違ふ。然れども上和ぎ下睦びて、事を論ずるに諧ひぬるときは、則ち事理自から通ふ。何事か成らざらむ。
十に曰く、忿を絶ち瞋を棄て、人の違ふを怒らざれ。人皆心有り。心各執有り。彼是とするときは則ち我は非とす。我是とするときは則ち彼は非とす。我必ずしも聖に非らず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫のみ。是非の理、ぞ能く定むべき。
相共に賢愚なること、鐶の端無きが如し。是を以て、彼の人瞋ると雖も、還りて我が失を恐れよ。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同じく挙へ。
十七に曰く、それ事は独り断ずべからず。必ず衆と與に論ずべし。小事は是れ軽し。必ずしも衆とすべからず。唯大事を論ふに逮びては、若しくは失あらむことを疑ふ。故に衆と相弁ずれば、辞則ち理を得む。
※憲法十七条は、奈良平安期に限らず鎌倉以降の武家政治にあっても奉じられ、戦国大名の分国法にも部分的ながら引用され、さらに千年以上後の江戸時代にも影響力を及ぼし、その公論(衆論)尊重、上下和諧を尊ぶ精神は五箇条の御誓文に繋がると花山信勝博士は指摘してゐます。
(前頁四段から続く)
第十条にはまた、人々はみなそれぞれの考へに固執するものだが、自分は正しいかもしれないし間違ってゐるかもしれない。誰もが共にただの人なのだ。どうして是が正しいと決められようか。だからこそ自分は正しいと思っても人々の言ふところに従って行ひなさい、と記されてゐます。「共に是れ凡夫のみ」「我独り得たりと雖も衆に従ひて同じく挙へ」といふ言葉にこもる謙虚な自省、それは第一条の「和を以て貴しと為す」と相まって人間への深い共感や愛情の発露であり、民主主義を越えて人の生き方を示す心でもありませう。
◇
民主主義もそれを支へる精神が滅びれば、ただの衆愚政治になるか、あるいは衆愚を利用した独裁政治となりかねない。国民自身が深く自分を見つめ、共に国のために生きる道を求めた先人の心と言葉に学ぶことこそ、暗夜にさ迷ふ日本を導く灯火となるやうに思はれるのです。
- 初出、平成22年8月 産經新聞九州山口版 -
(福岡市 原土井病院長)
はじめに
終戦直後、明治憲法が廃止され、日本国憲法が施行されたことに抗議して自決された憲法学者・清水澄博士に関する資料に改めて目を通し、博士の自決の意味することの重大さに思ひ至った。
時恰も、戦後60余年にして、国民の間にやうやく憲法改正の機運が釀成されてきたやうに思はれるが、博士がわが国体の護持と皇室のご安泰を願はれて、明治憲法に殉じられたことを、日本国民は末永く忘れてはならないと考へて一文を草する次第である。
最後の枢密院議長
清水澄博士は、明治元年石川県金沢市に生まれ、東京帝国大学法科を卒業後、学習院大学教授となり、明治38年法学博士の学位を取得し、宮内省、東宮御学問所の御用掛を拝命された。大正天皇、昭和天皇に御進講され、行政裁判所長官、枢密院顧問官を経て、終戦後の昭和21年6月13日、最後の枢密院議長に任ぜられた。
昭和21年10月29日、帝国議会を可決通過した明治憲法改正案は、引き続き枢密院の審議にもかけられ承認を受けた。博士は枢密院議長といふ立場から、占領軍総司令部主導のこの憲法改正案(占領軍総司令部起草の「日本国憲法」案)を認めざるを得なかったのである。
新憲法は11月3日(明治節)に公布され、6ヶ月後の昭和22年5月3日に施行されたが、施行後の9月26日早朝、熱海市伊豆山沖の定置網にかかった死体があった。漁民から連絡を受け駆けつけた熱海警察署長の片桐素一警視は、「懐中から二通の書面と一枚の名刺が出てきた。いづれも奉書の巻紙に墨書した立派なものだった。その顔は、実に神々しく、思はず合掌した。同行の係官は年間130件も変死人にあたってゐるが、こんな整然とした仏はなかったと驚嘆してゐた」と検死の模様を語った。
法学博士清水澄と書かれた名刺には、警察署長宛で「小生の自殺の理由は自決の辞のごとし。何卒、小生の遺骸は焼きて、遺族来たらばその骨を渡されたし。費用は所持する金子にてご出費下さい」と記されてゐた。
「自決の辞」
遺書は昭和22年5月3日の日本国憲法が施行された日に認められ(この前日に枢密院は廃止)、5ヶ月後の9月25日に自決された訳だが、「自決の辞」は、次の通りである。
|
「日本新憲法を制定するにあたり、 民間の学者及び団体に於ても、その私案を公表したるもの少なからず、其中には天皇制を廃止して共和制を採用せんとするの案なきにあらず。豪州及び中華民国並びにソ連邦の如き隣国に於て日本国の共和制たるべきことを主張するも、之に対応する策なきも、日本国民にして天皇制の廃止を主張するものあるは、実に遺憾の至りに堪へず。尚、国民中、戦争の責任者として天皇の退位を主張するものあり。殊に近時天皇が国民との間の関係を、一層親密ならしめる為、地方に巡幸せらるるにつき反対の意思を表明するものなきにあらず。従って天皇制の将来について大いに憂慮せざるを得ず。併し、小生菲才且つ追放の身にして、天皇制の永続と、今上陛下の地位とを確実にするを得ず。また実力なし。故に自決して幽界より、其目的達成に努力せんと欲す。之小生の自決する所以なり。而して自決の方法として水死を択びたるは楚の名臣屈原に倣ひたるなり 元枢密院議長 八十翁 法学 博士 清水澄 昭和22年5月 新憲法実施の日認む 追言 小生昭和9年以後進講(宮 内省御用掛として10数年1週に2回又は1回)したること従って龍顔を拝したること夥敷を以て陛下の平和愛好の御性質を熟知せり。従って戦争を御賛成なかりしこと明なり」 |
(昭和22年9月28日付 読売新聞)
抗議の矛先は日本国民へも
屈原は中国の戦国時代における政治家で、楚が秦の始皇帝に滅ぼされるとき、楚の将来に絶望して湘江の畔を彷徨ひ、汨羅の淵に入水自殺した。博士も新憲法における日本の将来を憂慮され、屈原の故事に倣はれたのである。
博士の令息の憲法学者・清水虎雄教授は、『明治憲法に殉死した憲法学者』(文藝春秋昭和39年11月号)の中で、「父の理想は、どこまでも天皇が君主であられることにあったので、新憲法が日本の歴史を無視して、連合国から押付けられ、天皇をロボツト化するものであることに怒りと不満を感じてゐた」と書かれてゐる。博士はご自分が大切なものと信ずる国体が、爲すすべもなく貶められることへ激しい憤懣を抱かれたが、抗議の矛先は、連合国の押付けに屈服した日本国民へも向けられてゐたのではなかったか。
昭和10年、美濃部達吉博士の天皇機関説が脚光を浴び、貴族院で政治問題として槍玉にあがった時、清水博士も美濃部説を鋭く批判した一人であった。美濃部説が天皇をもって国家の機関であると主張したのに対し、清水博士は、歴史的に天皇によって国家が創設され、以後、万世一系の皇統が継承されたのであるから、法理上の統治権の主体は天皇にあると主張されたのである。
国体と政体
博士は論考『逐条帝国憲法講義』の中で、「国体とは統治権の所在に拠りて分るる国家の特色を謂ひ、政体とは統治権行使の形式に拠りて分るる統治の体様を謂ふ」とされ「国体の変更は直に国家の消滅を来すも政体の変更は国家の生命に関するものに非ず」と書かれてゐる。換言すれば国体は日本民族のアイデンティティーを意味し、恒久性を保持するもの、他方政体は単に国体護持に資するものとして選ばれると理解して差し支へなからう。
更に博士は、「建国以来天皇を以て統治権の主体なりと爲す国民の確信深く未だ曾て其の信念の動揺したることなし。建国の初天祖天照大神、天孫瓊々杵尊に三種の神器を賜ひ勅して曰く『豊葦原の千五百秋の瑞穗の国は、是吾が子孫の王たるべき地なり。宜しく爾皇孫就きて治せ。行矣。寶祚の隆えまさむこと、当に天壌の窮りなかるべし』(筆者註。これは『日本書紀』で「天壌無窮の神勅」といはれる一文)と、皇統相紹ぎて統治権の主体たる観念、実に建国の大本にして国民の確信万古易らず。(略)之を我が国の国体と爲す」とされ、「国体」が建国以来の正統性と確固たる国民の確信に基づくと説かれてゐる。
明治憲法の第一条に、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とある。憲法を起草した井上毅は、後に変更されたが、初め、「日本帝国ハ万世一系ノ天皇ノ治ス所ナリ」とした。この「治す」は、井上が国典を研究してゐて、『古事記』の大国主神の「国譲り」の一節の中に、「しらす」と「うしはく」と二つの言葉が慎重に使ひ分けられてゐることを発見し、それから取ったものである。井上はこの違ひを、
「うしはく」といふのは、西洋で「支配する」といふ意味で使はれてゐる言葉と同じである。「しらす」は「知る」を語源としてゐる言葉で、天皇はまず民の心、すなはち国民の喜びや悲しみ、願ひ、あるいは神々の心を知り、それをそのまま鏡に映すやうに我が心に写し取って、それと自己を同一化させ、自らを無にして治めようとされるといふ意味である、と説明してゐる。
この天皇の御心にお応へせんとする国民との相互間のゆるぎない信頼は、「君民一体」の関係であり、正に「国体の本義」がここにある。
日本国憲法改正の眼目は…
このやうに明治憲法は、「天壌無窮の神勅」と「君民一体」の国民の確信に貫かれてゐたのである。
思ふに清水博士の自決の狙ひは、占領統治下で制定された現行憲法は無効であることを理由に、日本が主権を回復した暁には、即刻「憲法を破棄」すべきであると、日本国民へ託された悲願だと思はれてならない。
「新日本建設ニ関スル詔書」(昭和21年1月1日発布)には、
「茲ニ新年ヲ迎フ。顧ミレバ明治天皇明治ノ初国是トシテ五箇条ノ御誓文ヲ下シ給ヘリ」とある。
日本国憲法改正の眼目は、新しい「前文」の中で、「新日本建設ニ関スル詔書」に表現されたやうに聖徳太子十七条憲法及び「五箇条の御誓文」並びに明治憲法に触れ、全面改訂された新憲法が神武天皇創業以来の日本の悠久の歴史の王道に基づくことを宣明することであらう。
尚清水博士の故郷金沢市の護国神社境内には、『清水澄博士顕彰之碑』が建てられてをり、博士は東京の青山墓地に眠ってをられる。
(本会理事 前事務局長)
伊藤哲夫著 『明治憲法の真実-近代国家建設への大事業』
日本国憲法を讃へるといふ目的のために不当に貶められてきた明治憲法。しかし、その正当な評価を抜きにして、日本のあるべき憲法について論じることはできない。いかにして明治憲法は作られたか-いま学ぶべきは、明治維新を成し遂げた先人たちによる国家と憲法のあり方を巡るその壮大なドラマではなからうか。
税別1,400円 致知出版社
松村俊夫さんのご訃報に接し、驚きとともに残念な思いでいっぱいです。東京地裁の審議の最終弁論期日で意見陳述をしたことを昨日のことのように思い出します。
松村俊夫さんの勇気ある行動がなければ、私が政治家になることはありませんでした。松村さんへの感謝と追悼をこめて、ここに意見陳述全文を掲載させていただきます。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
意見陳述 平成13年12月21日
稲田 朋美
ここは、憲法において言論の自由が保障されている、日本の法廷です。
この国では、政治体制を批判することも共産主義を批判することも国旗・国歌を批判することも許されています。反体制であるとかブルジョア的であるという理由で逮捕されたり粛清されたりする国ではありません。
この国では、自分の国の歴史について誰かが決めた「ある一定の見方」があるのではありません。誰もが自由に歴史的事実の見方、解釈について議論をし、異なった意見をのべ、発表することが許されているのです。
松村俊夫さんは、まじめに定年まで会社に勤めた典型的な日本のサラリーマンでした。定年後ようやく時間ができて、自分が興味を抱いていた歴史について図書館通いをして研究をし、『「南京虐殺」への大疑問』という本を執筆しました。この本は松村さんが生まれて初めて執筆した記念すべき本でした。確かに松村さんは歴史学を大学で専攻していたわけではありません。笠原教授が指摘するように「歴史学研究」や「学問研究の方法」について専門的に学習し、訓練を受けたのではないのです。しかしそのような学習をし、訓練を受けた専門家だけが歴史を論ずることが許されているのでしょうか。そしてそのような学問を極めると必然的に「南京大虐殺はあった」という結論になるのでしょうか。答えは「NO」です。書証でも提出しましたが、最近、京都大学史学科を卒業し、中国近現代史を専攻する立命館大学の北村稔教授が『南京事件の探求』という本を世に出されました。同教授は南京事件を確定した重要な証拠資料であるティンパーリーとスマイスの著作が、第三者による中立的立場からの著作ではなく、国民党の戦時外交戦略のために執筆されていた事実を明らかにしました。さらに本件訴訟でも書証として提出されている洞富雄『日中戦争南京大残虐事件資料集 英文資料編』の中には例えば、「便衣兵の処刑」を「市民の虐殺」とするなど意図的、作為的としか思えないような誤訳があり、また同様に翻訳として適切を欠く部分が他にもあることを指摘しました。これは画期的な新事実の発見であると同時に「南京大虐殺」が例え日本や中国の子供たちの使う教科書に載っているとしても、未だ確定された事実ではないということを物語っています。
原告代理人は第1回の口頭弁論期日の意見陳述において次のようにのべました。
「被告松村俊夫によって認識されている『南京虐殺』という歴史的事実には、まさに被告そのものの『歴史観』『歴史認識の方法』、そしてそれを規定している被告自身の人間性と人間像が、如実に表現されているということができましょう。そしてその内実・実態が、なんであるかということは、この法廷で、本日より展開される審理過程によって白日の下に晒されるであろう」と。
本日、弁論を終結するにあたり、審理を振り返って、いったいこの裁判で明らかとなった松村俊夫さんの人間性と人間像はいかなるものであったのでしょうか。毎回被告席にすわり、たったいま自分の研究内容と心境を述べた松村さんは、この本の中でも、この法廷においても一度も原告を悪意をもって中傷誹謗したことも、原告の人格を傷つけるような発言をしたこともありません。本法廷で明らかになったのは、こつこつと資料を検討し、その結果疑問をもった南京事件の真実を知ろうと今なお研究を続けている一人の年老いた市井の研究者の姿ではなかったでしょうか。
反対に本法廷で白日の下に晒されたのは、松村さんに「右翼」のレッテルを張り、「資料批判について初歩的に無知」「資料を読み取る能力がない」「学問的常識をわきまえない」「著者のモラルを欠いている」「知的レベルが相応しない」「大脳皮質の発達が遅れている」と言葉の限りをつくして罵倒した原告支援者の人間性でありました。
1947年、谷寿夫中将を戦犯として裁く南京軍事裁判の法廷で、郭岐証人は日本軍がなしたとするさまざまな言語を絶する虐殺について証言をしました。そしてその後、被告人谷寿夫中将は、法廷中から罵声を浴びせられながら「これが、事実ならまことに残酷すぎる話です。しかし私はこれらの事実を知りません」と答弁したといいます。彼は、同年4月南京雨花台で銃殺刑に処されました。
それから50年たった日本の別件裁判法廷で、本件審理の陳述書において、そして多くの書物のなかで原告が1937年12月19日、南京において日本兵から受けたという暴行も、それが事実なら聞くものの言葉を失わせる悲惨で壮絶な内容です。
しかし、ここは敗戦直後の南京軍事裁判法廷ではなく、民主主義国日本の現代の法廷なのです。何人も原告の証言について疑問をもつこともそれを批判することも検証することも許されるのです。
そして原告は、単に一人の中国の年老いた女性ではなく、「南京大虐殺の鉄の証」という公の存在です。本件書籍における原告に関する記述は、公の存在としての原告の証言を検証した公正な論評(フェア・コメント)なのです。残念ながら原告の「名誉」が問題となっているこの法廷に、原告が日本の訴訟救助制度まで使って訴えたこの法廷に、原告は一度も姿をあらわしませんでした。私たちは、いったい原告がどのような翻訳書を読み、どの部分をどう理解して名誉を毀損されたと考えたのかを検証することも、1937年12月19日、南京でいかなる事実があったのかを検証することもできませんでした。しかし、松村さんのこの本を常識のある通常の人が読めば、この本の中の原告に関する部分は決して原告を個人的に中傷誹謗するものではなく、客観的立場から公の存在としてのすなわち南京大虐殺の鉄の証としての原告の証言および原告の役割を論評するものであることを理解できると思うのです。
日中戦争は日本と中国両国にとって不幸な出来事でした。そして南京軍事裁判と東京裁判で認定された「南京大虐殺」は戦後50年以上ものあいだ日中両国の上に重くのしかかる暗雲のようなものです。この暗雲に隙間を空け、南京事件の真実とは何かを検証することを目的として書かれた本件書籍の真意を汲み取っていただきたいと思います。そして、例え立場や見解はちがってもこのような名誉毀損訴訟という技巧的な方法により、南京大虐殺を疑問視する松村さんの言論を封じこめるのではなく、言論の場やペンによる論争を通じて真実を探求することが、憲法で言論の自由が保障されているこの国における正しい論争のあり方であると私は考えます。
(仮名遣ひママ)
※「南京事件」展転社を支援する会(福永武事務局長)
編註 松村俊夫氏裁判と稲田弁護士
所謂「南京大虐殺」がわが国を貶めんとするプロパガンダであったことは、地道な調査研究によって年々明白になってゐる。その一方で南京大虐殺を疑問符付きで論じると厄介なことになるぞ!と言はんばかりの訴訟が提起されてゐる。松村俊夫著『「南京虐殺」への大疑問』(展転社、平成10年刊)をめぐる訴訟はその好例である。刊行一年後の平成11年9月、「南京大虐殺の生き証人」とされる某女性から、著者と出版元は東京地裁に訴へられた。著書の中で、女性が生き証人にとして「仕立てられた」と書かれてゐるのは偽物扱ひで名誉毀損であるとの理由からであった。
地裁では、被告の敗訴となり、控訴するも棄却。上告審では一度も弁論が開かれることなく棄却(平成17年1月)。高池勝彦弁護士によれば、上訴棄却は著者にショックを与へたといふ。
松村氏の著書に関しては、もう一つの裁判があった。平成12年11月、今度は別の女性によって南京で訴へられたのだ。しかし被告に出廷の義務はなく、平成十八年八月、当然のやうに原告勝訴。司法権は特別の取り決めがなければ国境を越えるはずもないと思ってゐたところ、平成24年3月になって、南京での判決(日本円にして500万円超)の強制執行を求める訴訟が東京で提起され、をかしなことに地裁がそれを受理したため現在審議中である(この奇妙な「取り立て執行要求」裁判の問題点については、昨年の本紙3月号で詳述)。
著者の松村氏は昭和2年生まれ、7年間のニューヨーク勤務の経験をお持ちの元サラリーマンで日本古代史にも通じた在野の研究家だったが、昨年9月28日帰幽。「この裁判が松村さんの寿命を縮めたことは間違ありません」(高池弁護士)。
ここに転載した稲田朋美弁護士(現在、国会議員で国務大臣)の「意見陳述」は最初の東京地裁でのもので、敗訴の結果となるわけであるが、この意見陳述の直後、ある女性から名刺を差し出される。それは「所謂百人斬り競争」の新聞記事が証拠となって南京に呼び出され、昭和23年に処刑された人物の娘さんであった。そこで稲田弁護士はその遺族の「戦犯の娘とされた無念」を晴らすべく奮闘する。しかし判決では日本刀の機能からして百人斬りは疑問(新聞報道が虚報だった)としながらも、第一審敗訴で遺族を突き放す。かうした司法の実態に直面してゐた平成17年8月、稲田弁護士は出馬を請はれる。その際、政治家の怠慢が善良なる国民の歎きに背を向ける判決を招来してゐるのではないかと考へ、教科書内容の是正なども裁判所の役割ではなく、政治家の務めではないか、国家の名誉を守ることが政治家の重い使命であると考へるに至ったといふ。詳しくは同氏著『百人斬り裁判から南京へ』(文春新書)をご精読下さい。
(山内健生)
このたび私と同窓の後輩、石川一郎太氏(筆名。出村信隆氏、昭和五十五年富山大学理学部卒業、本会賛助会員)が小説『マジック消しゴム』三部作の完結編として、標記の一書を刊行された。これまで第一作『マジック消しゴム』、第二作『マジック消しゴム 創世記』(いづれも税別千百円、文芸社)が上梓されてゐた。
「マジック消しゴム」とは、もうひとつの世界とアクセスするアイテム(道具)で、タイムトンネルを想像してもらふと分りやすいかも知れない。子供向けのものではあるが、日本の国の歴史的な本当の姿を知って欲しいといふ著者の願ひが根柢にある。第一章「ヤマトタケルの時代」、第二章「聖徳太子の時代」、第三章「火焔のゲン」と続き、小説としてのフィクションも取り入れながら、そこに著者のこのシリーズに懸ける夢の結実を見る思ひがする。
このシリーズに第一作から登場する主人公はsたけるtとsあすかtといふ二人の少年少女であるが、そこには著者が、最後にヤマトタケルノミコトと、飛鳥を舞台にして聖徳太子を描きたいといふ当初からの夢が読み取れる。著者は本会にゆかりの深い黒上正一郎著『聖徳太子の信仰思想と日本文化創業』ならびに小生の拙編著『朗読のための古訓古事記』などにもよく心を傾けられて、自分の構想を検証されたやうである。
日本人の根っこ
このシリーズの第一作が発表されたのは今から三年前の八月、東日本大震災の発生した年であった。
著者は三部作の「あとがき」のそれぞれに「東日本大震災」を振り返る思ひを述べてゐる。第三作目の今回は次のやうに記してゐる。
|
《東日本大震災は未曽有の大災害であった。そのとき、東北地方の人々は筆舌に尽くし難い状況におかれながらも日本人の矜持を示してくれた。そこに日本人の誇るべき精神の発露があり、我々自身忘れ去ってはいけない本質があった。ならば、脈々と受け継がれた日本人の根幹は何に由来するのか? それを考え、至った事実は、己自身が自国の歴史、伝統、文化に無頓着なまま日常を過ごしていたということだった。しかし、この国に生まれながら、その誇るべきを知らずして過ごし終えるとしたら、それは実に惜しいことではないか。》 |
そんな著者の思ひが掘り起したのが、ヤマトタケルノミコト、聖徳太子といふ歴史上の二人の人物像であった。日本の古代史、古代文学に興味を持つ人々にとってはかなり著名な二人の人物像であるが、『マジック消しゴム』に登場する二人の主人公、“たける”と“あすか”のやうな少年少女にとっては、未知に近い人物像であることは確かであらう。著者が読者として最も期待してゐるのであらう少年少女たちが、この物語をひもといてくれたならば、きっと目を輝かせて読んでくれるに違ひない。本書を読みながら、著者の思ひに共感するところ大なるものがある。
火焔のゲン
今回の最終章に縄文時代の火焔土器をテーマにした一章が据ゑられてゐることにも興味を惹かれた。
「ヤマトタケルノミコト」や「聖徳太子」は文献(コトバ)を通してたどりうる祖先の遺産であるが、「火焔土器」をはじめとする縄文期の考古学的遺物は、文献は伴はないものの、実際に目で見ることもでき、手に触れることもできる遺産である。さうした異なった形での祖先の遺産の懸隔に、何となくジレンマを感じてゐたが、かうした創作(フィクション)の分野を借りることによって、その二つの世界が近づきうることを知らされた思ひがする。工業高校の教員として、在職中、“たたら”(古代製鉄)に取り組んだことのある自分には興味を惹かれる一話であった。
(岸本 弘)
第58回厚木合宿教室の報告集 『日本への回帰』第49集
「再生すべき『日本』とは何か」東洋紡(株)庭本秀一郎
「近隣諸国の動向と日本国ありやう」日本政策研究センター代表 伊藤哲夫
「古事記-神武天皇-」昭和音楽大学名誉教授 國武忠彦
「身を修める以て本と為す」寺子屋モデル代表取締役 山口秀範
「日本思想の核心と国柄」中島法律事務所・弁護士 中島繁樹
「短歌創作導入講義」大阪湾広域環境整備センター 久米秀俊
「創作短歌全体批評」羽後信用金庫石脇支店 須田清文
国民文化研究会Facebook開始
国民文化研究会は、1月23日からFacebookの掲載を始めました。
●アルファベットでインプットされる場合は、
https://www.Facebook.com/kokubunken
●日本語でインプットされる場合は、「公益社団法人国民文化研究会Facebook」。
これで国民文化研究会のFacebookページをご覧いただけます。
担当(お問ひ合せ先)島津正數
編集後記
巻頭で上村前理事長は60年前の春光寺合宿を回顧する。その報告集の標題『昏迷の時代に指標を求めて』は、そのまま今日の課題でもある。「先人を仰ぎその懐ひを受け継ぐ」との人生姿勢は尚、未だしである。教育も憲法も根はひとつだ。それに向けて我らの営みは続く。
(山内)