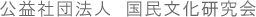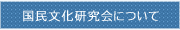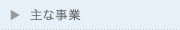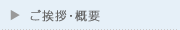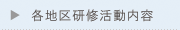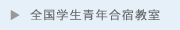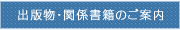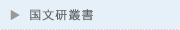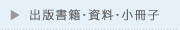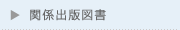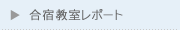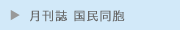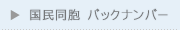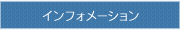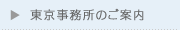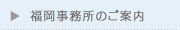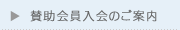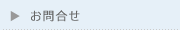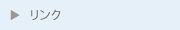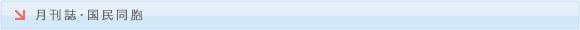
��T�V�U��
| ���M�� | �薼 |
| �V���@�摷 | ����}�����ł͓��{�����Ȃ� - ���������Ɗς��������Ƃ�Җ]���� - |
| �����@�S�i | ���z �䐹�^�̗��������F�肵�� |
�{�c�@�i |
������͖{���Ɍh��Ȃ̂��i��j |
| ����21�N �ԗ�Ռ��C���� |
�@����}�������������āA���R�̏��d���͍��A����ւ̏o�ȂƊe����]�Ƃ̉�k�ł��������A���O���ꂽ�ʂ�A���ɗJ�������D�o�ł���B
��A�������ʃK�X25���팸�̍��ی���́A���{�o�ς�j�]��������̂Ŏ����s�\�ł���A���ۓI�ȐM�����ĂɌq����B�����̗ǂ����Ƃ������Ĉꎞ�̊��S�ӂ��Ƃ͊O����ł��T�܂˂Ȃ�Ȃ����Ƃł��炤�B
��A��t����`�x�b�g��E�C�O���N���ɂ��Ă͉����ӂꂸ�ɁA�F���̔����̊�ɕ\�����ꂽ�u���A�W�A�����́v�\�z�́A�����𗘂��邾���œ��{�ɂƂ��ĉ��̗��v�ɂ��Ȃ�Ȃ��B�č��݂̂Ȃ炸�A�A�W�A�̍��X�⍋�B���邢�̓C���h�͂��̒�Ă��ǂ��~�߂��̂ł��炤���B
�O�A�č��Ƃ̑Γ��O�������ЂȂ���A�哝�̂ɑ����ĊԂ̌��Ď�������ѓ��{�̕����Ă��ӔC�ɂ��Ă͈�،������Ȃ������B
�l�A���A�ŁA�k���N�ɝf�v����Ă��l�X�̒D�҂��������E�ɑi�ւ��D�̋@����݂��݂��������B
�܁A���V�A�哝�̂Ƃ̉�k�Ŏl���Ԋ҂̊�{�I������q�ׂȂ������B
���N�Ԃ̐�̐���Ƃ���������p���������g�ɂ�鎩�s�j�ϋ���̓ł����{���ɐZ���������ʁA���鎞�����琭���Ƃ⊯���A�o�ϐl�ɍ��Ɗς����͂�A����w�����Ă�鎩�o�̂Ȃ��l�����ڗ��₤�ɂȂ����B
�@�@���a57�N�̋��ȏ��������ɒ[���ċ{�[�����k�b�ɂ���ċ��ȏ������ɒ�߂�ꂽ�ߗ��������A����5�N�̏]�R�Ԉ��w�W�������ʔ��\�̍ۂ͖̉슯�[�����k�b�B����7�N�̏I��50�N�Ɋւ��鑺�R�k�b�i���{��N�����Ƃł���ƒf�߂����j���X�̌��ǂ��ǂꂾ���傫�����A���ӂ܂ł��Ȃ��炤�B
�@ �ӗs�M�����L�̗������邽�߂ɖ����_�ЎQ�q���~�߂����]���A�F�B�̂��₪�邱�Ƃ͂��Ȃ��ȂǂƁA�����̓������Ɍ��������c�́A���Ƃƍ��Ƃ̊W�Ǝ��I�ȊW�����������B
�@����}�����ɂ͐l���i��@��v�w�ʐ����邢�͉i�Z�O���l�Q�������A�ڂ̗����Ȃ��@�Ă��ڔ������ł���A���̍�����j��뜜����ł���B
�@ ���̍���̎��ɑ������ĖY����Ȃ��̂́A�I����䌈�f�ɂȂ����A���a�V�c���A�s��ɂ����Ђ����ꂽ�����ɂ������ɂȂ����u���a21�N�̔N���ُ̏��v�ł���B���̖`���Ɍf����ꂽ�u�܉ӏ��̌䐾���v�́A�����V�c���ېV�����̌��ƂƏ���ɂ������ɂȂ����������{�̊�{���j�ł���A�S���͍��L�̒ʂ�ł���B�i���ʓ��͌�����j
��@�L�N��c���`�V���@���_�j���X�x�V�i�S�Ă̂��ƂɊւ��āA�����̎��I���Q�����������A���̋c�_�����Ă������j
��@�㉺�S����j�V�e���j�o�d���s�t�x�V�i��������S����ɂ��Đ������s���Ă������j
��@������r�����j�������e���u�����Q�l�S���V�e���}�U���V���������v�X�i�ǂ�Ȓn�ʂɂ��Ă��l�������̐E�ƂɌւ�������A���ނ��ƂȂ��A�F�����������Ɩڂ��P�����Ďd�����ł���₤�Ȑ���������j
��@�����m蛏K���j���V�n�m�c���j��N�x�V�i�Â�����̈�������������͉��ߐ��E�ɒʂ��镁�ՓI�ȓ����Ɋ�����������悤�j
��@�q�������E�j������j�c��U�N�X�x�V�i�m�����L�����E�ɋ��߁A�傢�ɓ��{�W�����悤�j
�@���a�V�c�́A���a52�N8��23���̋L�҉�ŁA�ْ��̈�Ԃ̖ړI�́A�_�i�Ƃ��������ӂ��Ƃ͎��̖��ł���A���̌܉ӏ��̌䐾���������Ɏ����čĔF�������邱�Ƃł������|�����q�ׂɂȂ��Ă��B
�@���a�V�c�͓��{�̐i�ނׂ������͂�����Ƃ������ɂȂ����B�������A���E�A�o�ϊE�A����E�̎w���҂͂��̂����t�ɐ^���Ɏ����X���邱�Ƃ����Ȃ������B�����ɁA�����̓��{�̔ߌ�������Ǝv�͂�ĂȂ�Ȃ��B
�V�c��S�̋��菊�Ƃ��ċ��ŗ������{�̍��������A���{�̗̓y�A�̊C�A�������A���Ƃ̊�Ղ��B�R�Ƃ��Ď�鐭���Ƃ̏o�����ɖ]�܂��B
�i�{������� ���� 69 �j
�@�@�@�@�͂��߂�
�@�命���̍����̑傫�ȊS���ł��������I�����I��A�������̕����̉��ɁA����}���S�̐V�������a�����₤�Ƃ��Ă��B����͑傫�Ȃ��˂�Ƌ��ɁA�]�������鎖���������܂��B���{�̌Â��ǂ����j�A�`���ɔw���������V�����̔����͂܂��ƂɊ��S�Ɋ��ւ܂���B���^���ނ̊�@��������������A�܂��ƂɗJ�����ׂ����ԂƎv�Ђ܂��B
�@�@�@�@���s���l�̉�
�@�������邨�悻1300�N�قǑO�̖��t�̉̐l�A���s���l�̉̂ɁA
�@�@�@�@�@
�y�Q�̍��̌�_�̂��炳�тčr�ꂽ�鋞����Δ߂���
�@�Ƃ��Ӊ̂�����܂��B���t�w�ҁA���{�F���́A���̒��w���t�̐l�X�x�Ƃ��ӏ��̒��ŁA���̂₤�ȉ�����Ȃ���Ă�܂��B
�u����͂��̐p�\�̗��i����672�N�j�̌�A���Ȃ��Ƃ�20�N�ʌo���Ă���́A�ߍ]�̍r�ꂽ�鋞���Â�z�̉̂Ȃ�ł��B�w�y�Q�x�Ƃ����̂͒n���A��Â̕ӂ̑����ł��B�w ���炳�тāx �Ƃ��� �̂́A�썰�̗V��������Ԃ�������ł��B�����獑���h����Ƃ����̂́A���̐_�삪����Ƃ������� �ł��B�Ƃ��낪���̍��̐_�삪�ǂ����ɂ������ƗV�����Ă��܂��āA�܂苕�E�̏�ԂɂȂ��Ă��܂��Ă��� �B���������r���Ƃ��Ă��邱�̐p�\�̗���̋����݂�Ƃ��܂�Ȃ��B
�w�y�Q�̍��̌�_�x���āA�܂茻���ɂ͂��U�r�ꂽ�p�����邾���ł��B��������l�͉��Ɨ��������ł��傤�B�y�Q�̍��y���x�z����_���A�����ǂ����ւ������ƍs���Ă��܂��āA�����čr��Ă���Ƃ�����ł��B ����͖ڂɌ����Ȃ����ۂ̔w�������ł���l�ł��B����͍��l�����̐��E�ł��B�N�ɂł��ʂ��鐢�E�ł͂Ȃ��B���l�̎�ς��݂߁A����ł݂������E�Ƃ����܂��B���y�̐_���ǂ����֗V�����Ă��܂����̂ōr��Ă���A�Ƃ����ӂ��ɂ��ނ��ݕ��Ƃ����̂́A�{���ɖڂ� �����Ȃ����ۂ̔w��A�����Ɏ����̐S�����ݒʂ点�Ă����āA�͂��߂Ăł���̂ł��v�i�T�_�M�ҁj
�@ ���t�l�A���s���l�̗�o�i��I���o�j�͑f���炵���Ǝv�Ђ܂��B�B���v�z�̌��㕶���ɉ������ꂽ����l�́A�Ƃ����ɂ��̗�o��r�����Ă��܂Ђ܂����B�������Ȃ���͂��ɂ���A���㕶���̍s�l��ɂ�钂�����̑ŊJ�A�����Đ��ޔ敾���Ă䂭�����B�̑��⒬�̕����A�������ɁA�Y�y�_�̑��݂��������Ȃ����ƂɋC���t���Ă܂��܂����B���y�̂��{�𒆐S�Ƃ����s����Ղ肪����ɓ`���̕����Ƌ��ɁA�J�Â����₤�ɂȂ�܂����B�Q�����Ă��l�X�̊��������Ƃ������������g�ɓ`�͂��Ă܂��܂��B�܂��Ɂu���y�̉h���͍��Ð_�̉h���v�Ƌ��ɂ���Ƃ��ӎ������N���Ă܂��܂��B
�@�@�@�@���̑厖�͏^���J�ɂ���
�@�����̋Ή��̎u�m�A���썑�b�̉̏W�̒��̌��t�ɁA�u���̑厖�́A�^���J�ɂ���A�傢�ɍ��J�������ׂ��v�Ƃ��ӌꂪ����܂��B
�@�u�^�v�Ƃ͐푈�̂��Ƃł���A�R���ł��B�u�J�v�Ƃ͍��J�̂��Ƃł���܂��B�V�_�n�_�A�c���ׂ̈ɑ���������������p��A�����̐_�X���J�邱�Ƃł��B���Ƃ̐����̍������Ղ������t�ł��B�^�i�R���j���J�i���J�j�́A���ƌ쎝�̓��{���_���{�̗v�ƂȂ���̂ł��B���Ɍ썑�̉p����J������_�Ђ̍��J�́A���ƂɂƂ��čŏd�v�ȍՓT�ł���A�������\���Ď��̑�����b�͓��R�����Q�q���ׂ����̂Ǝv�Ђ܂��B�܂��ɍ��̐����̌��_�ł���Ǝv�Ђ܂��B
�@�����V�c�䐻
�@�@�@
�_�_�@�@�i����43�N�j
�킪���͐_�̂���Ȃ�_�Ղ�̂̎�U��킷��Ȃ���
�Ƃ����ւɍ��܂���܂��V�n�̐_�̍Ղ�����낻���ɂ���
�@�ނ�ʼnE�̌䐻��q�u���܂�A���J�̑�Ȃ��Ƃ��̂ɖ��������Ǝv�Ђ܂��B
�@�����̓��{�́A���q�������݂���Ƃ͉]�ցA���K�̌R����ۗL���Ȃ��A���h���Ƃ��v�ւ鍑�Ƃł��B�܂������͈�U�ɋ}����`�E���ɕ�}���̐��_��Y�����Ă��܂Ђ܂����B�^�̓Ɨ����ƂƂ͐\���Ȃ�����ł��B�c���쎝�ׁ̈A�ꍏ�������R����ێ����A���h�ɓO���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv�Ђ܂��B�c����p�������̐��_�̕�����]��Ŏ~�݂܂���B
�@�@�@�@�l�A���ɐ_�����
�@�u�_�A�l�����ɔA�l�A���ɐ_�����v�B���̌��t�́A�����ېV�̌��M�A������b�i���C�j���̗L���Ȍ��t�ł��B�ꌩ��ʏ펯�Ƌt�̕\���Ɏv�ւ܂����A���̐^�ӂ͎��ۂɐ_��I�̌����Ȃ��A�_��̎��݂�g���Ȃđ̓�������b���g�̒ɐȌ��t�ł��B���B�͓��X�ڂɌ����ʐ_�̉�����ւ�A��������Ă�܂��B�_���Ȃ�������ɂ��Ă͂Ȃ�܂���B�c���̐_�X�͌��R�Ƃ��đ��݂��A���y�������Ă����ɏZ�ލ���������肵�Ă�܂��B���́u�M�v�̂��ƁA����_�X�̉��b��Y��T���ƂȂ��A���̌��t�����ɁA���S���ӁA�_�X��厖�ɂ���肹�˂Ȃ�ʂƎv�Ђ܂��B
�@�@�@�@�~�ނɎ~�܂�ʐ��̐S
�@���B��l��l�͂܂��Ƃɔ��͂ȑ��݂ł��B��������o���Ȃ�����A�u�����V�ɒʂ��v�Ƃ��ӌ��t��M���A�~�ނɎ~�܂�ʐS���ȂāA���ʂ�����{�̊�ǂɗ������͂˂Ȃ�Ȃ��Ɖ]�ӎv�Ђ����܂��B
�@���āA�ޗǂ̖�t���̊ǒ����Ȃ��ꂽ�A���c�D���t�́A���̒��w�s���̐l�E�����O�������x�Ƃ��ӏ��̒��ŁA���T�i�G�o�j�̒��̎��̊����I�ȋ��b�����p�Љ�Ȃ���Ă�܂��B
�@�u�q�}�����R���̒����ɁA�����|�����������������Ă���傫�ȐX������܂����B���̐X�ɂ͂�������̏b�Ⓓ���݂�ȂŒ��悭��炵�Ă��܂����B���錃�������̓��ł����B���̂��߂ɂ��ꂠ�����|�̖��C�����Ƃʼn��o�܂����B�܂���̋������̂��߁A�݂�݂邤���ɉ͎l�������ɔR���Ђ낪��A�����܂���ςȎR�Ύ��ɂȂ�܂����B���܂�ɉ₩�Ȏ��ł���܂����̂ŁA�b�B�͂��U�Q�Ăӂ��߂�����ł����B
�@ ���̎��A��H���_�����}�ɔ�ї����܂����B�����ĎR�̘[�̒r�܂Ŕ��ōs���܂����B���̒r�ő̂𐅂ɔG�炵�āA�܂����Ƃ̓����ыA��A�R���Ă���R�Ύ��̏ォ���S�ɉH��U���Đ��̓H�����炵�܂����B�����Ă܂��R�̘[�̒r�ɔ��ł䂫�A�G�炵���̂Ő����^��ł́A�H��U���ĎR�Ύ��̏ォ��H�𗎂Ƃ��܂����B��������\��A���S��ƌJ�Ԃ������܂����B���͐�A�ڂ͌������āA���ʂĂ܂����A�_���͂������߂悤�Ƃ͂��܂���ł����B
�@���̗l�q�������ɂȂ��ĕ����܂��A�_���ɂ₳�����w���O����̉H�ʼn^��ł������炢�̐��ŁA���̎R�Ύ��̉�������Ǝv���̂��ˁx�Ƃ������˂ɂȂ�܂����B�_���́w �����邩�����Ȃ����͎��ɂ͕���܂���B����ǂ���������Ȃ���Β��ԒB�́A�݂�ȏĂ�����ł��܂��܂��B������ �Ȃ��Œ��Ԃ����E���ɂ��邱�ƂȂǂƂĂ��ł��܂���B���Ƃ����ď����Ă����˂Ȃ�܂���B���ɂł��鎖�͂��ꂵ������܂���B�܂����B���Ԃ𒇗ǂ��Z�� �킹�Ă��ꂽ�X�ւ́A���̂ł��鐸��t�̉��Ԃ��͂��ꂵ������܂���B�����Ȏ��Ǝv���邩������܂��A�ǂ�������𑱂������ĉ������x�ƁA�����܂̑O���ї����āA�r�Ɍ������ĎR�� �[�֔��ł䂫�܂����B
���̎p���_���̌��t�ɕ����܂͐[���[���A�傫�����Ȃ�����܂����B�����ĕs�v�c�ȗ͂�����킳��܂����B����Ƃǂ��ł��傤���A�����_�����������Ƃ�����Ă��@�āA�J���~�炵�n�߂܂����B���ꂪ��J�ɂȂ�܂����B�������̎R�Ύ��������̂����ɏ�����܂����v�i�T�_�M�ҁj
�@����͈�̋��b��������܂���B�����������ɂ͏d��ȈӖ����邹���Ă�܂��B�Ђ����瓯�E���v�ЁA���E�ׂ̈Ɏ��̐��ۂ��l�ւ��A�Ȃ��g�Ɏ��Ă鐽���o���s���������܂��Ƃɑ����Ǝv�Ђ܂��B���̓��E���������^�̗����������炷��Ǝv�͂��ɂ͂����܂���B
�@�@�@�@�ނ���
�@���N�́@�V�c�É��䑦�� 20 �N�A�܂��@�V�c�c�@���É��̌䐬�� 50 �N�̂܂��Ƃɖڏo�x���c�ꂷ�ׂ��N�ɓ���܂��B����������ĕ�j�����A�܂��܂��̌�c���̌���ׂƍc���̖�h�����F�肵�����Ǝv�Ђ܂��B�䐹�^�̈�w�̗������F�O���ě߂݂܂���B
���� 21 �N 9 �� 10 ���L
�i�F�{�s�ݏZ�E�{��Q�^�@���������Z���t�@���� 86 �j
�@�@�@�@�h��ɉ��ւ�ꂽ�u�������v
�@�u������v�Ƃ��ӌ��t�́A�܂�����Ȃɂ͒m���Ă�Ȃ����炤�B�����A���́u������v�Ȃ�ꂪ�ŋߏ����ÂL�܂��Ă����B���^�̍��ꎫ���ɂ͂܂������Ȃ��₤�����w�L�����x��w�厫�сx�Ƃ�������^�����̍ŐV�łɂ͍ڂ��Ă��B�u������v�̌�Ƃ��Ă̈Ӗ��́A�u���̂��Ƃ�������ďq�ׂ�v��Ƃ��ӂ��Ƃ��B���߂ĕ����l�͂���Ȍ��t������̂��Ƃ��ӊ��z�����ŏI���Ă��܂ӂ�������Ȃ��B�ǂ��Ƃ��ӂ��Ƃ̂Ȃ��l�{���Q�̌��t�̂₤�Ɏv�͂�邩������Ȃ��B�������A�������ق����Ȍ��Е��ɂȂ邪�A�������̌��t�����{��̌h��̑̌n�����͂����̂��Ƃ�����A����ȂɈ��ՂƂ��Ă͂���Ȃ����炤�B
�@�����R�c��ꕪ�ȉ�u�h��̎w�j�v�\�����͕̂���19�N2���̂��Ƃł���B�����ł͏]���̎O��ނ̌h��i���h��A������A���J��j�ɁA�V���ɔ�����ƒ��d���2��ނ����ւ��v5 ��ނɂȂ��Ă�B���̂��Ƃ��o���Ă�������邾�炤�B�����Ԃ����Ȃ����Ɗ������Ȃ��������炤���B
�@���̂₤�ȋ敪�ł���B
�@�@�@
�P ���h
�@�@�@
�Q ������ �T
�@�@�@
�R ������ �U�i ���d��j
�@�@�@
�S ���J��
�@�@�@
�T ������
�@ ���\���炵�炭�o���A���܂łǂ̂₤�Ȕ������������̂��B�Ǖ��ɂ��ďڂ����͒m��Ȃ��̂����A�ŋߖ{���ɍs���āA�V�����o���h��W�̖{����������Ɏ���Ă݂���A�݂Ȃ��̓��\���ӂ܂ւ����̂������B�����ꂪ�v���Ă�ȏ�ɐZ�����Ă��Ă��Ƃ̈�ۂ������������B���ꂩ������ƍL�܂肱�����ꐊ�ւ邱�Ƃ͂Ȃ��Ɉ�ЂȂ��B
�@�w�Z����ɂ����ɉe�����Ă��₤�ł���B������ɂ��āA���܂łǂ�قǂ̋c�_���Ȃ��ꂽ�̂��B�����c�_�̗]�n�͂Ȃ��̂��B���ۂ͔�����Ƃ��ӌ��t���̂�m��Ȃ��l�������̂ł���B
�@�@�@�@�u������v�o��̎���v��
�@ �u������v�Ƃ��ӌ�̓o��́A������قڔ����I�O�̏��a30�N��ɂ����̂ڂ�B���錤���҂̘_���Ɏg�͂ꂽ�̂��n��炵���B�Ȃ����̌ꂪ���ꂽ�̂��炤���B���̔w�i�ɂ��āA���ꂱ��ƒ��ׂ邤���ɉ��ƂȂ������Ă������Ƃ�����B
�@����́A�I���̎Љ�́A�V������������T�铮���̈�Ɋ֘A���Ă��B����܂ł̓��{��g���̏㉺�\���̂͂����肵�Ă�K���Љ�ł������Ƃ��āA���ꂩ��̐V���������`�Љ�ł͖��含�ɂӂ��͂������t���K�v�ł���A�Â����t�͉��߂Ȃ���Γ��{�̉��v�͂ł��Ȃ��Ƃ������_���Ɩ��W�ł͂Ȃ��Ƃ��ӂ��Ƃł���B
�@�����ł͌h��̎g�p����㉺�W�ɂ������Ƃ͔ے肳���ׂ��ł���Ƃ���A����ɑ�͂�V�����T�O�Ƃ��ĕ����A�e�a�A���Ƃ��ӂ��Ƃ������o�����B���̑��ɐ����A���E�ȂǂƂ��ӌ��Е�������Ă��B���Â�ɂ���A�l�͑Γ��ł���Ƃ��ӊϔO�������ł��o�����̂ł���B
�@���݂܂ŘA�ȂƂ��đ������������l�֕��̔w�i�ɁA�����R�c��ꕶ�ȉ�̑O�g�ɓ����鍑��R�c��A�����i�h�ꕔ��̕���͋��c�ꋞ���j�̏��a27�N�ɁA�����̕�����b���ĂɌ��c�����u���ꂩ��̌h��v�̊�{���j�����邱�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̖`���ɁA�h�ꂪ�u������ɔ��B�����܂܂ŁA�K�v�ȏ�ɔώG�ȓ_���������v���A�u���̍s�����������܂��߁A��p�𐳂��A�ł��邾�������E�ȑf�ɂ��肽���v�Ƃ�����ŁA���̂₤�ɏ�����Ă�B
�@�u����܂ł̌h��́A��Ƃ��ď㉺�W�ɗ����Ĕ��B���Ă������A���ꂩ��̌h��́A�e�l�̊�{�I�Ȑl�i�d���鑊�ݑ��h�̏�ɗ����˂Ȃ�Ȃ��v
�@�����ċ�̓I�ɁA�u���v�̕t��������A�s���ɍ������h���s���ɒႢ����������܂��߂���A�Θb�̊���u�ł��E�܂��v�̂Ƃ��邱�ƂȂǁA���܂��܂Ȓ��s�͂ꂽ�̂������B���̒ɉ����āA����Ȍ�̌h��̕ϑJ������A�l�X�̌��ꐶ���ɂ��傫�ȉe����^�ւ��ƌ��͂�Ă��B
�@�@�@�@�A�����J����g�ߒc�́u�����v
�@ ���̂₤�Ȍ��c���A�Ȃ��o���ꂽ�̂��炤���B��ÁA�s���f�g�p�̗v���Ɋ�Â��ď��a21�N�i1946�j 3����{�ɗ���������ꎟ�A�����J����g�ߒc�̕������Ȃ���Ȃ�Ȃ��i���̕��͗�������ꃖ�����o���Ȃ����������ɒ�o����Ă��B����ɂ��Ă��A���Ƃ�Â��Ȋ��Ԃɏo���ꂽ���炤���j�B���̕��̒��ŁA�����`�I�ȋ��琧�x�́A�l�̑����Ɖ��l�Ƃ̏��F�̏�Ɋ�b�������Ƃ��āA������v�̂��܂��܂Ȋ����E���s�͂ꂽ�̂������B�����Ƃ͂��ցA����͐�̌R�̖��߂̂₤�Ɏ���A����ɉ����ċ����{�@�͂������A�Z�O���A�j�����w�A�o�s�`�ȂǁA�u���݂̊w�Z����Ɋւ��鐧�x��A���@��A���e��̂قƂ�lj����������A���̕��ɂ���ĐV�������̍��ɍ̗p���ꂽ�v�i������w�A�����J����g�ߒc���x����@1979�N�j���Ƃ����߂Č���K�v������B
�@ �u����̉��v�v�ɂ��Ă��A���̒��Ɉ�͂��݂����A���Âꊿ����S�p���A���[�}�����̗p�����ׂ����Ƃ��Ă�̂ł���B���̒�Ă����͂������Ɏ��{����邱�Ƃ͂Ȃ��������A�Ȍ�A������v�̔g�͑傫�Ȃ��˂�ƂȂ��āA����܂ł̂��̂���Ђ���И�ɏグ���A�����̎��̂≼�����ЂȂǁA������u���v�v����@�^����C�ɍ��܂������Ƃ͎��m�̂Ƃق�ł���B���̔N��11���ɂ́u���ォ�ȂÂ����v�Ɓu���p�����\�v�i1850���j������i���t�����j����A�Ȍ�A�u���犿���v�u���p�������̕\�v�u���p�������P�\�v�Ƒ����B���R�̂��Ƃ��u�h��v�ɂ��Ă����������Ȃ����B�ے肷�ׂ�������f������̂̈�Ɍh�ꂪ���ւ��A�u���ꂩ��̌h��v�̌��c�ɂȂ������̂ł���B
�@�@�@�@�u������v�Ƃ͉��Ȃ̂�
�@�������Č��c�����10�N��̏��a30�N��A�V����̌h��ɂӂ��͂������̂Ƃ��āu������v�Ƃ��ӌꂪ�V���ɍl�֏o����ēo�ꂷ�邱�ƂɂȂ����B
�@�u������v���咣����x������Ă��������̔w�i�ɂ́A�E�̂₤�Ȑ��̓`���y���̗���ƌl���d�̔��z�����邱�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����A������v�̓����ɑ���ᔻ���₤�₭�\�ʂɏo�Ă���̂��A���a30�N�߂��ɂȂ��Ă���ł���B�c�����̖����w���̚��ꋳ���x�i���݂͕��t���Ɂj�����s���ꂽ�̂͏��a 35 �N�̂��Ƃł������B
�@ �܂����W���i�����w�K�@��w�����j�́w���{��̔N�ցx�i���a41�N�j�̒��ŁA���{�̕��j���u�\���Ȓ������Ȃ��i�߂��v�u�w��I�ȗp�ӂ��s�����Ă����v�ƒf�肵�Ă��B��؍F�v���i�����c����w�����j�́w���Ƃƕ����x�i���a48�N�j�̒��ŁA��ɂ������u���ꂩ��̌h��v�ɂ��āA�u���{��̌���I�����̐������ώ@�Ɋ�ĂȂ��ꂽ�Ƃ������A��̌R�̈ӂ��āA�摖��������̖��剻���Ӑ}�I�ɂ͂������ӂ��������Ɍ�����̂ŁA�K���������ׂĐM�p����������̂Ƃ͌����Ȃ��v�Ə����Ă��B
�@���āA�u������v�Ƃ͂����������Ȃ̂��B�u�b��̂��̂��Ƃ̕\�����Ƃ����āA�b�肪�����̂��ƂÂ����̕i�ʂւ̔z��������킷��v�i�{�n�T���j�Ƃ��ӂ��Ƃ����A��̓I�ɂǂ�Ȍ�������̂��炤���B����̕����R�c��ꕪ�ȉ�\�ł����Ă��Y����̗�́A��Â��Ɂu�����v�u�������v�̓��ɂ����Ȃ��B���ɒN�𗧂ĂĎg�ӂƂ��ӂ��̂ł͂Ȃ��A�u���̂��Ƃ��A�������ďq�ׂĂ���v�Ƃ��Ӑ����������B
�@�u���v��u���v�Ȃǐړ��ꂪ�����̂́A�݂Ȕ�����Ƃ݂Ȃ��Ă悢���Ƃ��ӂƂ����ł͂Ȃ��B�u�������v�u�����O�v���͑��h��ɁA�i���Ă�ׂ��l�ւ́j�u���莆�v�͌�����ɂȂ�Ƃ��ӁB����̎�̂⓮��Ɋւ���l�����l�ւ��āA���ꂼ���ʂ���邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ����ł������ώG�ł킩��ɂ�����ۂ����邩��A��������l����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�@�@�@�@�Ȃ��h��ɂ���K�v������̂�
�@����ɂ��Ă��������ďq�ׂ邾���Ȃ̂ɁA�Ȃ���������ւČh��Ƃ��Đ��ւ�̂��炤���B���̗��R�ɂ��āA�u�搶�͂����������オ��܂����v�Ƃ��ӂ₤�Ȏ��A�u���v�Ƃ��ӂ����u�����v�Ƃ����������ӂ��͂����B�u�z�����ďq�ׂ�v����h��Ƃ��Ĉʒu�Â���̂��Ƃ��ӁB��������ƁA�z����������̕\���͌h��ɂȂ肤��Ƃ��ӂ��ƂɂȂ�B���������̂₤�ȉ��߂܂ł��āu������v���A�Ȃ��V���Ȍh��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��i�]���̎O��ނł����������Ƃ��ӂ̂Ɂj�B���������Ƃ��ĔF�߂Ă��A�����̐l�͂��ꂪ�h��ł��闝�R���قƂ�Ǘ����ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�ӁB
�@�u���p�����v�Ƃ͓��ʂ̎��v�ɉ��ւ鐧�������̈��ł���A�����̔p�~������ɓ���Ă�B���ꂪ�����ɍ��͂��p�~����A���a56�N�Ɂu��p�����v�ɕύX���ꂽ�B�������Ђɂ��Ă��A���a61�N�Ɂu���㉼�������v�̉��肪�s�͂ꂽ�B��シ���́u������v�v�͕s�\���Ȃ��猩�����⌟�����Ȃ���Ă������A�����������Ōh��Ɋւ��Ă����́u���ꂩ��̌h��v�̊�{���j�i���a27�N�j�̉�����ɂ����Ď�����Ɏ��c����Ă��B
�i�k�C���D�y���ˍ��Z���@ ���֔N 60 �j
�@���{�w������A���_�Ȋw���������тɍ�������������ɘA�Ȃ镨�̎t�F�̌������J�肷��P��̈ԗ�Ղ� 9��21���A�����E�ѓc���̓�����_�{�ɉ����āA��⑰���͂��߉���A���h�����Q���̎Љ�l�E�w���� 58 �����Q�āA���߂₩�Ɏ���s�͂ꂽ�B�{�N�͐V���ɐA�؋�B�j���A�R�c�P�F���̓����J���ꂽ�B�ՋV�ł͍��Ă̌��؍��h�����̏I��������A�ꓯ�́u�_�F�s�Łv�u�i�߂��݂̂��v����Ĉ�w�̌��r�������А\���グ���B���Ɍ��r�̂̈ꕔ���f����B
��@�F |
|
| �����s�@ ���V�b�q�� | |
| �@�@�ꂷ���ɒ��`�̓����т��đ���{�����Â��� | |
��⑰ |
|
| ���]�s�@ �u���� | |
�@�@�J�����ĉ߂�����Ē��̉��̕����ԗ�Ղ̎��ɂȂ肯�� |
|
| �@�@�@�@�@�@�R�c�P�F�搶 | �{���s�@ �R���K |
�@�@�_�a�Ȃ�݂̒��ɂ��z�Ƃ��������������v�Џo���� |
|
���c���s�@ �ΖȔ͎q |
|
�@�@�@�@�@�@���a19�N7��16���A�Ō�̉��{��o�q |
|
�@�@�Ăт͋A�鎖�Ȃ���`�ɂĒ�グ���ӂ݂�����₢���� |
|
��茧���g���@ ���{�̂� |
|
�@�@�J�����Ƃ̏d�Ȃ���X�̐S�d���ԂƂ�ږS�Z�ƒǂЂ����Ȃ��� |
|
�X�s�@ �����r�� |
|
�@�@�Ȃ������Ȃ��ݗF��̂ݖ��Ăׂ����ւ܂����Ɏp���ւ��݂� |
|
�����s�@ ���c���l�Y |
|
�@�@������ɉ������ʉe�Âт݂��܂̂ӂ�������F�邩�� |
|
�����s�@ ���c�����j |
|
�@�@�c���ɋt�g���J�ӂׂ����܂����w�ގt�̂��ւ� |
|
�v���Ďs�@ ���ы`�V |
|
�@�@���̖{�̍��̊�Ȃ錛�@�������������v�АȂ� |
|
����s�@ �����a�F |
|
�@�@�������܂̂�܂Ƃ̉̂�����������F���ÂԂ��ӂ̓� |
|
�s�@ ������Y |
|
�@�@���[�Ɍ��t�������ď\�ܔN�_�ƂȂ肵 ���̏Ί�Ɍ��� |
|
| �@�@�@�@�@�@���̔���� | �������s�@ �{�e�V���Y |
�@�@�ӂ邳�Ƃ̓y���̏��̏d���J�����̓��L�������ǂ݂��� |
|
���c�s�@ �����S���q |
|
�@�@���̖{�̓������ނ�ᶂ��ꂵ��B�̐Ռp���Ă䂩�܂� |
|
�{���s�@ ��L�۔� |
|
�@�@����̎c����������ǂݕԂ��s���ׂ����̂���ׂƂ����� |
|
�����s�@ �ʼnz�F�� |
|
�@�@����̑�l�̈⓿�����̔N���W�ЂČ��u��Ƌ��� |
|
| �@�@�@�@�@�@�R�c�P�F�搶 | �F���s�@ ���c�ޕF |
�@�@�̂��邱�Ƃ̊y�����������ӎt�̌�p�͍������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�R�� ���Z | ��t����S�@ ���C���F |
�@�@�N�����Ďl�N�߂���ǂ��܂���ɌN���ݐՂ��Âт�܂��� |
|
| ���s�@ ���p��� | |
�@�@���̔N���J�����Ƃ݂̂̑�����nj����炯���Ƃ����F��Ȃ� |
|
���l�s�@ ���엺�� |
|
�@�@���̔N���Q���������Ă��₵������낪�݂܂鍡���̂��̓��� |
|
�������s�@ �㑺�a�j |
|
�@�@�N���Ɏt�̌N�F��݂܂���Ď₵�������ʍ����̂ݍ� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�䑦�ʓ�\�N��j�s�� | ���l�s �����L�O |
�@�@�����̐����������V�c��悬�܂�ސ������� |
|
�s��s�@ �������� |
|
�@�@���̂��܂͂��͂�䂭�Ƃ����͂炴��܂��Ƃ̐S���Ă䂫�Ȃ� |
|
| �@�@�@�@�@�@�A�؋�B�j�搶 | ���s�@ �V���摷 |
�@�@���̉���_�升�h�ɗU�Ђ܂����\�N�O�̎t�̌N�Â� |
|
�F���s�@ �ēc�`�� |
|
�@�@��l�݂̂����˗��������������Ђ�����Ɍ�肷���܂� |
|
�F�{�s�@ �����S�i |
|
�@�@�t�̌N�̑������ւɓ����ꋤ�Ɋw�т����X�������� |
|
| �@�@�@�@�@�@���c���Г�Y�搶 | �R���{���s �{�c���� |
�@�@�t�̌N���Âт܂���܂��Ȃ�ӂ����݂Ȃ����v�Џo����� |
|
���֎s�@ ��粐��v |
|
�@�@�p���䂩�ނݑc�̂��ƂЂт����ӂ���̍��h���܂��_ |
|
�����ێs�@ ���i���V |
|
�@�@�݂��܂�̂����Ђ������킩����ɂ��ւ䂭�����킪�Ƃ߂Ȃ� |
|
�����s�@ �Ⓦ��j |
|
�@�@�����̉p��ɋF�炸�����]�ӑ����ɐ_�̉���͂Ȃ��肵 |
|
�}����s�@ ���Y�ǗY |
|
�@�@�N���o�ċ��ւ����l�X�̌䉶�͂���ɐ[���Ȃ�䂭 |
|
| �@�@�@�@�@�@�R�c�P�F�搶 | �F�{���e�r�S�@ �O�闘�� |
�@�@������������፷���ɏ݂����֏��q�w�������܂Ђ� |
|
| �w�@�� | |
���{�@���N�@ ���V�@�� |
|
�@�@�@�@�@�@�f��u�����̐�m�v��q������ |
|
�@�@��y�͐����ɂē��u��Ɗ���P�����u�`�������� |
|
��ʑ��N�@ �R�����Y |
|
�@�@�H���ɂ��邷�ׂ�̖��悬���˂����錎�̌��������� |
|
�ҏW��L
���R�̓j���[���[�N�ł̓�����k�Łu���R�k�b�v���P��\���A�u���A�W�A�����́v�\�z���q�ׂ��Ƃ��ӁB����͐�t�����Ɏ~�܂炸���m���������_�ӊj���������B�����_�ЎQ�q���ւȂ��������Č��������ނ̏p���ɓU��̂��B���S�Ɋ��ւȂ��B
�@
�P��̈ԗ�Ղ��c�܂ꂽ�B���X�ɓǂݏグ�����Ր_�̌䖼�ɁA�����̏d�݂ƘA�Ȃ�҂̏d�����߂����߂Ċ������B �i�R���j