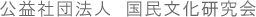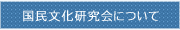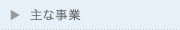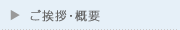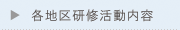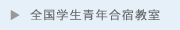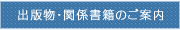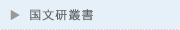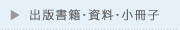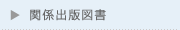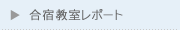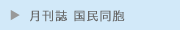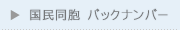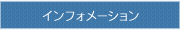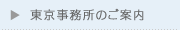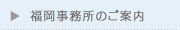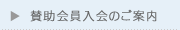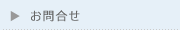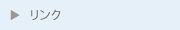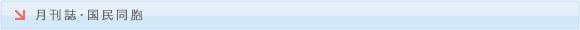
��T�U�X��
| ���M�� | �薼 |
| �ѓ����j | �u���Z�o�ϐ���v�ɂ����������Ɗς��s���� |
| ����g�� | �b�Ƃ��Ă̋߂ƐT�݂̔O |
| ��粐��v | �����ېV ���̕��S�l�\�N -�w�^��x�i������\�N�\���s�j����- |
| �����h�F | �����я��i36�j |
2���~�̒�z���t�����荞����20�N�x��2����\�Z��1�����A�^�}�����̏O�@�ōċc�����ꐬ�������B
����21�N�x�\�Z�����l�̌o�܂ɂȂ�Ǝv�͂�邪�A��2����\�Z�֘A�@�Ă̎Q�c�@�R�c�����������C���ł���ɒx��A��z���t���̔N�x���x������Ԃ܂���ƕ��Ă��i2���������݁j�B
��������u�����v���ӂƂ����Ă��A���̍����͐ŋ��ł���B������g���Ĕ��Е�������A�l����L�ьi�C��������Ƃ̍l�ւł��炤���A���ɐȐ����I���z�ł͂Ȃ��炤���B����Ɋt���͎��̂��A���Ȃ��̂��A�ȂǂƖ��߂̋c�_���W�J���ꂽ�B
���ꂪ�c�O�Ȃ��猻���킪���́u���Z�o�ϐ���v��1�ʂł���B�����ƋB�R�Ƃ����u���Ɗρv�ɑ����������ł��o���ĖႢ�����Ƌ�������Ă��B�u�����S�v�Ɓu���������Ɗρv���K�v�Ȃ��Ƃ́A�����A�O���A���S�ۏ����ł͂Ȃ��B�o�ρA���Z�A�בւ��R��ł���B
��������ꂸ�Ɍ��ւA�R���͂��o�b�N�ɂ��Ȃ������A�O�������蓾�Ȃ��̂Ɠ��l�ɁA�ݕ��̋������R���͂ɔ�Ⴗ��B�Ȃ��u�ăh���v�����E�́u��ʉ݁v�ƂȂ蓾�Ă��̂��A�m���Ɂu���[���v���͂����Ă͂�邪�A�����ʉ݂��u���E�ʉ݁v���炵�߂Ă��͕̂č������ł���B
�ČR�����E�ŋ��̌R���ł��邱�ƂƖ��W�ł͂Ȃ��͂��ŁA���̓_�ɂ��ē��{�ł̓}�X�R�~�ł���w����ł���ӂ�Ȃ��B ��Ԓ��߂́u�i�C��ތ��ہv�͕���9�N�i1997�j���痂�N�ɂ����ẮA���͂��u���Z�s���v�ł������B������N�ɂ͖k�C����B��s�E�R��暌����j�]���A���N�ɂ͒����M�p��s�E���{���M�p��s���j�]�B
����ɉ䂪���̌o�ϐ��������}�C�i�X0.8���ɓ]�����B���̎��̎匴���͉��ł��������B�ܘ_�A����ł�5���Ɉ����グ��ꂽ���߂ɏ���}���ɗ������i�C�������Ȃ����ʂ͂������B�������A���ꂾ���ł͂Ȃ������B���{�����Y���t�̂��̎��̃L�[���[�h�́u�O���[�o���X�^���_�[�h�v�ł���A�u���Z�r�b�O�o���v�Ƃ��ӌ��t���������B
���̐܂̃O���[�o���X�^���_�[�h�̓T�^�͋�s�̂a�h�r��̃N���A�ł������B���ꂪ���E�̋��Z�r�b�O�o���ɑΉ�������M��̐������ԓx�ł���Ƃ���Ă�B ��̓I�ɂ͍��ی��ϋ�s�i�a�h�r�j��Ƃ��͂����̂ŁA��s�̑ݏo�����z��Ƃ����Ȏ��{�q�Ƃ���䗦���A8���ȏ��B�����Ă�Ȃ���s�����ۋ��Z�s�ꂩ����ߏo�����Ƃ����ł������B
���̔����Ƃ��Ӑ����́A���傤�Ǔ��{�̎��Ȏ��{�䗦���������鐔���ŁA���Ă̋�s�͂�����N���A���Ă�B ���ꂪ����9�N�̌i�C��ނƏd���āA��s�͕��q�ł��闘�v�A�܂莩�Ȏ��{�̏[����}�邱�Ƃ͓���A���̋����ȁu�݂��a��v�A�͂��܂��u�݂������v�Ƃ��ӌ��ۂݏo�����B
���q�̊g��͖����Ȃ̂ŁA����̏k���ɓw�߂��̂ł������B���Z��@�̓����ł���B�U��Ԃ�A����̓W���p���o�b�V���O�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��A�u�O���[�o���X�^���_�[�h�v�́A���Ȃ͂��u�A�����J���X�^���_�[�h�v�������̂ł���B ����̋}���ȁu�i�C��ށv�ɍۂ��āA��s�̎��Ȏ��{�䗦���]�X���Ă�鍑�����邾�炤���B�č��̑�\�I��s�ł���V�e�B�o���N����Ԃ܂�Ă��킯������A�a�h�r��ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��B
�܂�u���E�I�ȃX�^���_�[�h�v�́A���̊�̒��S���̓s���ɂ���āu�ω������v�������̂ł���B ����ł́A�������Ď~�܂Ȃ����E�i�O���[�o���j�ɂ����āA��i�X�^���_�[�h�j�Ƃ��ׂ��͉��ł��炤���B����͎��������̍��̊��ێ��������邱�Ƃ������蓾�Ȃ��B�����̕����Ɠ`���A�����Ď��������̈ӎu���������鍑���^�̓Ɨ����Ƃł���A���ꂪ���E�ɒʗp���鍑�̂�����Ȃ̂ł���B�D�s���ɍ��E����Ȃ��m���Ƃ����u���Ɓv��ڎw���������̂Ƌ����O���Ă��B
�i�V���d�ށi���j�햱����� ����57�j
�������V�C�R���т̈⏑
���a20�N8��19���A�����s�x�O�̖��R�Ŏ������V�C�R���сi�������_�w���݊w���Ɋw�k�o�w�j�́A�s��̐ӔC�l�ł��鎩�����g�ɕ��͂�āu��鮃g�R�V�w�j�@�c���j�����e��铃����V���v�Ƃ̈⏑���c���Ď������ꂽ�B
���āA�c�܂�邻�̈ԗ�ՂɊw�����ォ��Q�Ă������A�u�V�c�É��ɒ�������v�z���_�v�̂܂܂ɐl����S�����ꂽ�������т̐������ɓ��ۂ̔O������Ă����B���̎v�Ђ͍����Ɏ�����ς�Ȃ��B ���т̎v�z�S����c���ꂽ�⏑�̒�����Â��B
�@�u�c�������N���@�É��m���j��གྷJ�i�ߊ��m���݃����V�@���l�m�����V���t�w�L��a�������@�ރJ�R���j�σk���j�����@�֒m�V�}�c���X�g嫃������j�����@���c�j�]�t�w�J���X�v
���т́A���u�̓c���L���⏬�c���Г�Y�搶���Ƌ��ɁA�哌���푈�u���ȑO����א��҂̐푈�w�����j�̍��{�I���ׂ�ᔻ���Ă����B���̂��Ƃ́u�ރJ�R���i�č��̌R���j�j�σk���j�����֒m�V�}�c���X�g嫃��v�ƋL����Ă��ӏ�������@������B
�J�ւĂ�ʂ�A���ƍň��̔j�ǂ��}�ւ邱�ƂƂȂ����B�����|�c�_���錾�̎���ɂ���āu�ꑽ�����@�É��̌��ɊO���̎i�ߊ������̂������Ďd���ӎ��ԁv�����������̂��B�����āA���́u�߁v�������g�ɕ��͂ꂽ�̂ł������B�u�ꎀ�ȃe�b�J�߃��ӃV���Z�e�鍑�R�l�^���m�h�_���ۃ^���g�X�v�Ƃ��⏑�ɂ͔F�߂��Ă��B
���āA�����̎��B�ɂ́u�鍑�R�l�^���m�h�_�v�����ƂȂ��A�������ۓI�ȊT�O�ƂȂ��Ă͂�Ȃ����炤���B���̂��B����͎��B���{�l��l��l���u���{��������̉h�_�v��@���ɕۂׂ������A�Ȃɓ˂����ė��Ȃ���������ł͂Ȃ��̂��B
�A�C�f���e�B�e�B�E�N���C�V�X������錻�݂ł��邪�A�u�É��̌��ɊO���̎i�ߊ��̗��̂��������v�������������āA�u�ێ炷�ׂ����́v�����ł��邩����S���瑧�������邱�Ƃ͏o���܂��B���̓��{�ł́A���[�_�[�B�̒��ł��ցA�u���{�̌�����A�����J�̌���̕������ƂȂ��i�D�ǂ��v�Ƃ��������U��ӎ��Ȃ�������͂��҂����Ȃ��炸����A�������B���́i�匠�r���j�Ƃ��Ӎ��ƓI�ߌ�����ڂ��ӂ������u�����Ȃ̕t�������v�̂₤�Ɏv�͂�ĂȂ�Ȃ��B
�@�v�z�̓_���Ƌᖡ�̕K�v��
�@�É��́u�F��v�ւ̖�����
����É��́A�c���q�a���̎���̏��a61�N5��26���A�c���ƍ����̊W�ɂ��Ď��̂₤�ɋL�҉�ŏq�ׂĂ�����B
�@ �u�V�c�������̏ے��ł���Ƃ�����������A���z�I���Ǝv���܂��B�V�c�͐�����������ɂ́@�@�Ȃ��A�`���I�ɍ����Ƌ�y�����ɂ���Ƃ������_�I����ɗ����Ă��܂��B ���̂��Ƃ́A�u�a�̗��@�@�s��Q�[�ɓ������āA�����̈�����F�O���鍵��V�c�ȗ��̎ʌo�̐��_��A�܂��A�w���A���́@�@����ƈׂ�ē����ӂ��Ɣ\�͂��B�r������ɂށx�Ƃ�����ޗǓV�c�̎ʌo�̉����Ȃǂɂ���Ă��@�@�\����Ă���Ǝv���܂��v�i�w�V�V�c�Ƃ̎��摜�x���|�t�H�j
����É��́u�����Ƌ�y�����ɂ���v���̂��Ƃ��A�g�߂ɂ͏��a�V�c������{�Ƃ��Ď��H���Ă�����B
�É��̂������Ђ�z��������Вn�̍������A�ő�̐����I���͂���������b�̎��@�Ƃ͎����̈�ӑ傫�Ȑ��_�I��܂����Ă�邱�Ƃ͓����ҁi��ւ��R�Îu���̒��������������A�w�c���ƐN�x10�����j�����Ƃ���ł���B
�����Ƃ̈ꎞ�I�E���I�Ȏ��@�Ƃ͈���āA���U�����̎l���q�E�ΒU�ՂɎn���đ�A���̑��P�܂ŁA��Ɂu�������ꖯ������v�ƋF�O���Ă�����É��̂������ЂɁA��Ў҂͖����́u�^�S�v�������Ă�邩��ł͂Ȃ��炤���B
�Ƃ��낪�A�ێ琭�E�̃��[�_�[�Ƃ��ڂ����Ό��T���Y�s�m���͎����w��������c���x�i�����ЁA����6�N�Łj�̒��Ŏ��̂₤�ɏq�ׂĂ�B
�@ �u�����牽�\�N�Ɉ�x�Ƃ�����N�̗�Q�ɂ���Q�[�̎��ɂ́A�V�c�͍ЊQ�n�̌䌩������@�@�A�c���O���Ȃǂ����A�������ʼn����Ԃ��������肵�Ēf�H�����A�����̂��ߎ��n�̂��߂ɋF�@�@�����Ē��������ƁA���Ȃǂ͎v���܂��B�^����т₩�ȍc���O�������A�����ɑ����ċF���́@�@�s���I����ꂽ�V�c���A�q�Q�ڂ��ڂ��ł��Ă��܂������p�����킳��邱�ƂŁA�����͗����@�@�����h�ӂƑ���������ł��傤���A�����̋y�ʐM�����悹����Ǝv���܂��v�i�S�\�O�Łj
���̐S��܂点�y���ǂ݉߂��Ȃ���̎咣�������ɂ͂���B
�@�V�c�͍ЊQ�n�ɕ�����A�����ŋꂵ�ލ����������ӕK�v���Ȃ�
�A�u����т₩�ȍc���O���v�͕s�v�ł���̓�_�ł���B
�u�c���O���v�Ƃ��ӌ��Е����̂��}�X�R�~�p��ł���A�����Ŏg�͂�Ă��u����т₩�v�Ƃ��ӌ`�e�����\�f��^�ւ���̂Ŋ��S���Ȃ��B�O���͐��{�̐ӔC�ōs�ӂ��̂�����A�É��̊O�����K��͐T�d�ł���˂Ȃ�Ȃ����A���K�⍑�Ƃ̐e�P�F�D�Ɍv��m��Ȃ����̂ݏo���Ă�邱�Ƃ́A�����e�n�ւ̍s�K�Ɠ��l�ł��炤�B
���́u�����v�ɋ߂��L�q�𐳖ʂ���ᔻ���w�e�����l�͏o�Ă��̂��炤���B���́A���T�w���B�Ƌg�c���A�搶�̕��͂�֓ǂ��Ă�邪�A���̈�߂��v�Џo�����B
�@�u�����Ɍە�������m�̏팾�ɁA�w���̎m�͐̂̎m�̗l�ɗE�҂Ȃ邱�Ƃ͏o���ʂȂ�A�������^�@�@�Ȃ�x
�t�]�ӎ҂���B�]�r���̌������ށB�Ȃ��E������p���A�������^�E�V���ɕ����A�s���s�@�@�F�A�s�m�s�`�A�F���^�E�V���ɂȂ�Ȃ�B�����������܂��邱�Ƃ��v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�u��ⲋL�x�u�k�Њw�p���Ɂj
���A�搶�͂��̐l�����v�z��\���������t���u�r���ށv�Ɖ]�͂��B�l�Ԃ����߂Ƃ͉]�͂�Ȃ��B���z�̍����������Ă��u���t�v�ɐ^���Вf���Ĉ��ނׂ��v�z�͋����킯�ɂ͍s���Ȃ��A�Ɓu����O�v��厖�ɂ��Ă�����̂ł���B
�A���璺��̍ł��d���ӏ�
�܂��A�Ό����͓��������̒��Łu����v�̑���ɐG��Ď��̂₤�Ɍ��ӁB
�@�u���ǍŌ�͂��������R�~���j�e�B���܂߂�����ɍs�������Ǝv���B�����Ă��܂ł͂��ē��{�l�@�@���厖�ɂ��Ă������ڂ̋��炪�܂������Ȃ���Ă��Ȃ��B��O�́w���璺��x�������o���Ă��ā@�@���A���܂ł͒N�����Ă��Ȃ����A�V�c�����ڂ̋���ɏ��o������܂����낢��Ȗ����N���@�@�Ă��邾�낤�v�i�O�f��206�Łj
��O�ɉ��āu���璺��v�ڂ̋���݂̂ɏI�n��������d���������̂ł͂Ȃ��̂��B���璺��̈�ԑ�ȂƂ���́u�����b���Ƌ�Ɍ��X���^�i�����S���ɂ����������ĖY��Ȃ����Ɓj���ę���������ɂ��Ƃ�����Ӂv�Ƃ��ӁA�����Ƌ��ɍ��݂�ڎw�����Ƃ��ꂽ�����V�c�̂��p���ɂ���B���̓_���������Ă͋��璺��͕���Ȃ��B
����ꕽ���̖��͍����ł��É��������Ɓu��Ɍ��X���^���ę���������ɂ��Ƃ��v��͂�Ă�邱�Ƃ��䐻��ʂ��Ĕq���邱�Ƃ��ł���B���̂��Ƃ�������Ǝ~�߂�Ȃ�A�E�̂₤�Ȉ�߂��@���ɋȂ��̂ł��邩���邾�炤�B
���͏��a48�N�t�A���Z���@�ɂȂ����B�ȗ��A�����_�O�Ɍ䐻�Ƌ��璺���q�u���ċ��d�ɗ����Ă����B�q�u����x�Ɂu���b���Ƌ�Ɂv�̏��ɗ���ƁA�����V�c���s�я���g��Ɓu��Ɂv�ƌĂт����ĉ������Ă��₤�Ɋ������ċ����������Ȃ�B
���̎��ɕ����Ă���u�䐺�v���{�R�̊�тƂȂ�A�������玄�̌p������u�ƕs���̐M�O�́A����Ă���̂ł���B
�����ېV���J���������̗�
�Éi6�N10��2�������A�]�˂��璷��ւ̓r���A���ɂČ䏊��q�������A�搶�́A���̊���������Ă�����B
�@�@ �u�q�P荁v
�R�͋ݑю��R�̏�A
�@�@
�������Ƃ��Ē鋞�����͂���Ȃ��B
�@�@
����ᷚu���ĖP荂�q���A��l�ߋ����čs�����Ɣ\�͂��B
�@�@
�P荎⛌�ɂ��č��ÂɔA���R�݂͂̂���ĕύX�Ȃ��B
�����Ȃ炭���㐹���̓��A
�@�@
�V���h�Ж������ގ�����蔭�����ӁB �i�ȉ����j
�u�P荁v�Ƃ͍F���V�c�������Ȃ���Ă�鋞�s�䏊�̂��Ƃł���B�F���V�c�́u������ӂɖ��₷����Ƃ����Ӑg�̂��T��ɂ��T��ٍ��̑D�v�Ƃ��r�݂ɂȂ��Ă�B
�A�����J�̃y���[���Y��ɗ��q���Ĉȗ��A�V�c���u�����Ђ̍��i�ߑO4�����j���ʑ̂��։����A�G���ە��A�����̈�������F��Ȃ���v�Ă�邱�Ƃ��m����24�̋g�c���A�͂܂��邪�������߂ʕ��ŁA�䏊��q�����̂ł���B
���̐S�̖ڂɂ́A�ʍ����̏�ɐ������O�z��n�ɂ҂���ƕt�����܂܂̓����ʏ��A�̎p��������₤���B�q��͔@���قǒ����������Ƃ��炤�B���A�搶�͉��́u�ߋ����čs�����Ɣ\�͂��v�Ȃ̂��H�@�䏊�̐����ɑS�g���k�֗N������߂��݂̗܂��~�܂�Ȃ������̂ł���B
�u�ߋ����čs�����Ɣ\�͂��v�Ƃ��ė�����ʍ����ɐ��ݍ��܂����A�]�˂��疾���ېV�ւƎ�����������̗͂������̂��B�����Č�����Ȃ��X�̌�������́A���̍����I�ȗ͂͐���͂��Ȃ������̂ł���B �i���������������Z���@ ����62�j
�����ېV�Ƃ��ӑ厖�Ƃ��������Ƃ��͂��̂́A�c��3�N���얋�{�̑吭��ҁA����̉������ÁA���������N�i1868�j�̌܉ӏ��䐾���̔��z�A�X�ɖ����l�N�̔p�˒u���Ɏ���܂ł����ӁB���̊ԁA�F���V�c����i�c��2�N10��2���j�A�����V�c��H�N�i�c��3�N1���j������B���N����20�N�i2008�j�͈ېV���琔�ւ�140�N�ɓ���B���Ȃ�ɐU��Ԃ��Ă݂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
140�N�Ƃ��ւΒ����₤�ŒZ��������B�l�Ԉ�l�ɂ��Ă݂�ΐ����I���̓I�Ɍ��E���Ă��B���������̔�����70�N�Ƃ��ւ��̍��͐l�Ԏ����̂������B��������70���߂����l�ɂƂ���70�N�O�͎x�ߎ��ρA���ꂩ��哌���푈�A�s��A���ƂȂ��Ė������ʂ̎v�Џo�A�ꂵ�݁A�������܂������ċL���͗������̂ł͂���܂��B
���ɂƂ���70�N�O�͏��a13�N�i1938�j�A���w�ܔN�A17�˂ł���B�x�ߎ��ϓ�N�ځA��_�ɕ�܂�Ă䂭�����͔����������A�ӎ��̒�ɂ��������̂́A�c���̍����琢�ԁA�ƒ�A�w�Z�ɂ��������������ɑ��閳�����̐��h�ł͂Ȃ������炤���B
�Ў�Ȏq�������������w�㋉�̂���A�搶�Ɉ�������Ēd�V�Y�̍�������A�֖�C���𓌏シ������͑��������������Ƃ�����B���͓����̍b�ɌR�����Đ��������Ɍ����Ċ��Ă��Ċ���U�����̂��B�ォ��ォ�瑱���R�͂��C����g�������������B�c�ȐS�ɊC�h���{�̈Ќ����S�ɏĂ��������̂��B
�w�Z���̂ł́u�A�������v���������B�u�����C����ї���e�ۍr�Q��Ӄf�b�L�̏�Ɉł��т������̋��ѐ���͉�������͋�����v�w�|��̐����̓N���X���|��ł�����B������A��ċA�炤�ƓG�e�������A�ł̑D���𑖂��肻�̖���A�Ă��Đ��ɐg�͈�Ђ̓���𗯂߂ĎU�����B���̗D���������A���V�A�̏����ɂ���͂ꂽ���{�m���B�������ӜA�������̈�ۂ͐搶�̘b���畷�����̂��炤�B
���w�Z�̐搶�͂������Әb�����Ă��ꂽ�̂��B�T�ؑ叫�ɂ��Ă����̗����U���̐S�ɋ�S�A�u���d�䉽�m��A�c�e�J���V�j�ŃG���B�M���������l�J�҃��v�M���̎��A�}���̎����v���ċ����̌ØV�����͐܂ɂӂ�Č�������̂��B�搶���e�B���A�R���v�z���`�����̂ł͂Ȃ��B�����������܂܊������܂܂��q���Ɍ�����̂��B��X�͂��̂₤�ɂ��č��̗��j���K�����̂ł���B
�����ېV�͎q���i���w���j�ɂƂ��Ă��ꂩ��X�ɑk��70�N�O�̂��ƁA�������͂����̂��S���o���Ă�Ȃ����A���y�̐�o�ҋg�c���A�̖��O����������Ɍ��т��Ă��B�ւ�Ƃ��ĕĊ͂ɏ�荞�ݓn�q����Ă����ƁA�����̑卖�ŌY���������ƁA�������m�̖�킪�����̌��M�ɂȂ������ƁA����ʂ̂��Ƃł͂��邪����͂��肻�߂̎��ł͂Ȃ��B���j�̊̏��A���ɂ̏�Ɍ��т������K���Ă�̂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
���č��̎q�������͂ǂ��Ȃ̂��炤�B�����ېV�A��������A���a�̑��A���̂��Ƃ��ǂ����ւ��Ă��̂��炤�B
���ւ��Ă�Ȃ����ƁA������q�������̒m��Ȃ����Ƃ���ׂĂ݂悤�B��x�E�x�߂�Ȍ����Ă����O���R�̗͂��U�Ɩ��{�̐���̎��A�F���V�c���ǂ�ȂɌ�S�ɂ����w�͂��ꂽ���B�����V�c���R�l���@���o���ꂽ���ƁB���璺����o���ꂽ���ƁB
����{�鍑���@����̋�S�ƁA���̏o����������̂͐��E�������̋Ƃł��������ƁB�����V�c�䐶�U��93,000�]��̌�̂��₳�ꂽ���ƁA���̈�ւ����ւ��Ă�Ȃ����ƁB�X�ɑ吳���a���̓��{�𒆐S�Ƃ��Ă݂��x�ߓ����ƁA�R�~���e�����ƁA�A�����J�̓����B�哌���푈�I���̌�ْ��̂��ƁB
�������ӓ��{�̕��݂̃L�C�|�C���g�ɐG��Ȃ��ŁA�����ېV�ɂ���ē��{�́u�ߑ㍑�Ɓv�ւ̕��݂�i�ƁA���ȏ��͏����B���̖ڕW�́u���R�A����v���Ə����B�R������̗͂ŋߑ㍑�Ƃւ̓��������̓��{�́A�����̌��t�ŖڕW�������Ă��̂��B�������N�ɖ����V�c���_�O�ɑt�ス��ꂽ�u�܉ӏ��̌䐾���v�ɂ͂�������B
�u�����m蛏K���j���v�u�m�������E�j�����v�u�㉺�S����j�V�e�v�u���@���_�j���V�v�����S�Ă��u�e���m�u�����v���܂��₤�ɁA���܂��锬������l���𑗂�܂��₤�ɂƁA�V�c���V�n�_���ɂ����ЂȂ��ꂽ�B
�����č������\���ėL����{���ǂ܂ꂽ���ɂ́A�u�����m�}���A�i���m��b�A���m���j�o�d�x�J���U���A�b���ރ~�e�b�|����ՃV�c�v�̌��t������B���R����̒����͑��������܂��Ă��̂��B��������ɋA���A�ېV�����Ƃ��閾�����N3���A�����R���]�ˏ�ɓ���ꃖ���O�̂��Ƃł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@
�����ېV�Ɩ�������͉��ł������̂��B�q���S�Ɍ��C��^�ւ�₤�ȕ��͂����ȏ��ɂȂ�����A�ЂƂ̕��͂������Ɍf����B���q�V�S�́w���{�̖ڊo�߁x�̕��͂ł���B���q�V�S�́A�吳2�N52�˂ŖS���Ȃ������p�w�Z�n�n�ҁA���{���p�̉��l�𐢊E�ɑi�ւ���o�҂ł���B�w���m�̗��z�x�w���{�̖ڊo�߁x�����p��ŏ����ă����h���A�j���[���[�N�ŏo�ł����B���I�푈�̑O��̂��Ƃ��B
�@�u���{�����m�̈ꍑ���Ƃ��ċߑ� �����̋��낵���}���ɉ����悤�Ɠw�͂��Ē��ʂ����d���͍X�Ɂ@�@��w����Ȃ��̂ł����B��X����������ڊo�߂�u�Ԃ܂ŁA�����x�ߋy�ш�x�ɑ�����Ɓ@�@����̍�����Ԃ���X�̏�ɂ������Ă�B�c���ė����D�̍]�˘p�o���͑傫�ȋ��n�ł��@�@���B
�@�@�c����܂ł킪�����I���o�̒��ɐ���ł���j�I���_�́A������v�R��邪�@���\���@�@�ƂȂ�瞂�o�Â邽�ߑ����̎������҂Ă�̂ł���B�c�����ĉ䂪�����̗��j��n�߁@�@�āA��c�`���̉䂪���y����邽�ߔ@���Ȃ������̂�ׂ����ɏA���āA�M�˂̕ʂȂ��A�@�@����Ƃ��Ӎ������������B��X�͈�̂ƂȂ��A�����āq�����̖�r�́q�����̌��r�ɉi�v�ɏ��@�@�����̂ł���B�v
�V�S�̕��͂ɂ�����₤�ɁA�����̍���ŊJ�̐擪�ɗ����ꂽ�̂́A�����V�c�̌䕃�É��F���V�c�ł������B���ł͑����̗��j�Ƃ����F����Ƃ���ł��邪�A�w�ߐ����{�����j�x�S���̒��ғ��x�h��͑�������ꌩ����\�����Ă��B�H���u�ېV�̑�Ƃ𗧔h�Ɋ����������͂́A�F���ł��Ȃ��A���B�ł��Ȃ��A�����̑喼�ł��Ȃ��B�������̎u�m�ł��Ȃ��B
���������V�c�̕��N�ɂ��点���T�F���V�c�ł���B�v�u�R��ɈېV�̗��j����������l�X�́A���M�Ƃ����Ƃ����āA�b���̓�����ލ��\�����A���̉^���̒��S�ƂȂ点��ꂽ�A�F���V�c�Ɋ��ӂ���邱�Ƃ̂Ȃ��̂��A�r���⊶�Ɏv�ӂ̂ł���B�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@
����140�N�O���L�O���āA�F���V�c�̌䐻���ƁA�F���V�c�́u��q���꒟�v�̈�߁i���v2�N�i1862�j���炨�����ɂȂ����ߐb�ւ̌䏑�ȁj�ƁA�����V�c�́u�����ېV�̛��ˁv�̈�߁i�������N�i1868�j3��14���j�̈�߂��ދL�������B
�@�@������ӂɖ��₷����Ƃ����Ӑg�̂��T��ɂ��T��ٍ��̑D�i�������N�j
�@
���܂����ʐ��ɂ킪�g�͒��ނƂ��ɂ����͂����Ȃ��Í����i�N���s�ˁj
��q���꒟���u�Ⴕ�R�炸���ėB�Ɉ��z�Ƒ������ɏ]�ĉ��߂��A�C���敾�̋ɁA�Ђɏ^���̏p���Ɋׂ�A�����Ȃ���G�����r�ɋ����A�u�Ӊ����炸��x�̕��Q�܂A�����ɉ����ȂĂ���c�ݓV�̐_��Ɏӂ����B
�Ⴕ���{10�N��������āA�������ɏ]�ЁA�^���̎t���Ȃ�����A�����ɒf�R�Ƃ��āA�_���V�c�_���c�@�̈��F�ɑ��Ƃ�����S���ƓV���̖q���i����j�𐃂ЂĐe������Ƃ��B��������z�̈ӂ�̂��Ē��ɕƂ��v��B�v
�����ېV�̛������u���ʒ�����V�̎��ɂ�����A�V�������A��l�����̏����鎞�͊F�����߂Ȃ�A�����̎��A������g����J���S�u���ꂵ�߂�䅓�̐�ɗ����A�×�c�̐s�������Ђ��F�𗚂݁A���т��߂Ă����A�n�ēV�E��ĉ����̌N���鏊�ɔw������ׂ��B�v
���ɁA63�N�O�A���a20�N�i1945�j���哌���푈�I���ْ̏��̈�߂��ދL����B
�@�@�u�c�҃t�j����隠�m��N�x�L��� �n�Ń����q��i���Y�B���b���m�� ����P�N�V���m���B�R�@�@���h���� �n�A���^�m���N���A���w��L���� �w�E�r��L���E�r�ȃe�ݐ��m�׃j �������J�J���g�@�@�~�X�B ���n䢃j��铃��쎝�V���e�A���ǃi�����b���m�Ԑ��j�M�߃V�A��j���b���g���j�݃��B�@�@�c�X�V�N������ƁA�q�����`�w�A�m�N�_�B�m�s�Ń��M�W�A�C�d�N�V�e�����L���O�q�A���̓����@�@���m���݃j�X�P�A���`���ăN�V�u�����݃N�V�A���e��铃m�������g�V�A���E�m�i�^�j�ヌ�U���@�@���R�g�����X�x�V�B���b���������N���K�Ӄ�铃Z���B�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
140�N�O�̔�����70�N�O�����a13�N�Ŏ���17�˂̎����ƍŏ��ɏ������B���̍����獡�Ɏ���N���́A���̎v�Џo�̋l�������̐l���ł���B����͑����A�킪���̐푈�Ɣs��Ɛ��̐l���ɑ��Ȃ�Ȃ��B������߂����ėF������A�ƒ낪���萶�����������B���a�V�c�A����V�c�́A���̎���̐܁X�̎��R�Ɩ���a�̂ɂ��r�݂ɂȂ��Ă��B
�݂�Ȃ���v�ӂ��Ƃ́A�V�c�É������A�펀�������ƁA���܍݂鍑���Ǝl�G�ɋP�����R�Ɛ����������Ȃ͂��A��ʂɍ݂点���ӁB�����ދL�������a�V�c�I��̌�ْ��̈�߂́A�܂��Ɍ��ݑ����̍����ւ̂��@���ł���B
���̑��S�́A140�N�O�A�����ېV�̎��̓V�c�̂����t�ɒ������Ă��B��̔@���Ɋւ炸�A�_�ӂ��܂�č��̐擪�ɗ����A�m���̑��S�Ŗ������낵�߂����ӁB�ېV�̐^�����ŎO���������₵�����t������B
�u�\���V���n�����҃g�v�t���Y�������҃g�v�t�x�V�A�������j���q�V�^�K�c�e�����A���ԃj��N��މ�䅋ꖁ�㐋�j�ꎡ�j�A�X�v�́u�ꎡ�v�̌������u��铁v�ɋ��ߋ��ЁA����u��铃��쎝�V���e�v�Ƌ���ꂽ�̂��I��̑�قł������B140�N�O�A�������Âɂ��V���{�J���̑���j�́A�����̓��{�Č��̂��@���Ɉ�т��Ă��̂ł���B
�i�{�� ����88�j
�Ғ��E�ԊԐ_�{�_���c���j����Ɂu�^���v�@�֎��w�^��x��73���q�����ېV140�N���W���r
����20�N12��25�����s-���ځA �����́��A�t���K�i�A�����͕ҏW���œ��ꂽ�B
�v�ǗY�̂䂭�Ăӓ����䂫�ɂ䂫���߂܂�ߑ��S
�����h�F�͌F�{�o�g�̊C�R�R�l�ŁA�哌���푈�u���̗��N�A���a17�N5��������s������ʍU���������B�V�h�j�[�p���}�P�������̎l�ǂ̈�������̒����ł���B������сi�펀�㒆���j�́A�G�̔����U���ő����������コ���A�E���ɂ��i�ߓ�����g�����o���G�͂ɑ̓�����U����������A�����Ƌ��Ɏ����������ɉv�ǗY�ł������B
���̉̂͏o���O��3��29���A�R�̋@���̂��ߏo���̂��Ƃ͔邵�A�S���邩�ɕʂ�������悤�ƉƑ������ɌĂ��ɁA���e�ɓY��𗊂݂Ȃ�����Ⴕ���̂ł���B���l�Ƃ��Ă̓����s���ɂ߂ēV�c�É��̌�S�������ߐ\���グ�����Ƃ��Ӌ����ӎu�����߂��Ă��B���̔N�̉̉�n�Ŕ��\���ꂽ���a�V�c�̌䐻�́A���̒ʂ�ł���B
�@�@�@�@�@�@���u�A���_�v
�@�@
��Â����قӂނ�_�ӂ����̂͂₭�͂�ւƂ������̂�Ȃ�
���ӈÉ_���Î�����_�̕��@���Ђ�����ɋF�����̂ł���B���̓V�c�̌�[�J����������Ǝ~�߁A����𐁂����ӕ��̈�Ƃ��ėE��簐i���悤�Ƃ����̂ł���B�O�N�n���C����P������ꎟ���ʍU�����̊C�R�����l���ɍs�͂�A�V������Ɏi�ߒ����R�{�\�Z�́u�v�Ǖv�̂䂭�Ƃӓ����䂫���͂߂킪��l��ЂɋA�炸�v���f�ڂ��ꂽ�B�킪���l�͊F�����v�Ђł������̂ł���B
���́u�܂�����̓��v�͌×�����̓`���ł��邪�A���B�ɂ͓ޗǎ���̓V��������z���ꂽ�����V�c�̌䐻�����p�����\���ł���B�V�c�͕Ӌ��h�������̂��߂ɔh�������ߓx�g�Ɏ��̌䐻���������B
�@�@��v�̂䂭�Ƃ��ӓ������ق납�ɔO�Ђčs���ȏ�v�̔� �@
�d��Ȏg����S���Ă�����v�����ɂȂق���ȋC���ōs���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɖ��߂�ꂽ�̂ł���B���̎���ɁA���l�Ƃ��Ďd�֕��s���̐��_��唺�Ǝ����A�唺���́u�����āv�Ƃ��Č������̂��A�u�C�s���@���Ђ��r�@�R�s���@�������r�@��N�́@�ӂɂ������Ȃ߁@�ڂ݂͂����v�ł���B
���{�l�̐�Ђ́A��ʂ̔��e�ŕ����I�ɓG�E���邱�Ƃł͂Ȃ������B�����ɂ͏�ɑ��S�ɕ��Е���Ƃ���ЂƂ̓��̎������ӎ�����Ă�B
�i���ۗ����@�\�����������卸�@�P �M�O�j
���u�����я��v�́A�F����̈��u���Ă��Z�̂��A�A�ڂł��Љ���������ł��B�F����̂����e�����҂����Ă���܂��B
�V���Љ�
�����P���{���{��c �Ғ�
�w���{�l�Ƃ��Ēm���Ă��������c���̂��Ɓx
�o�g�o�������ŕ� 1500�~
�V�c�É��䑦��20�N���j���Ċ��s���ꂽ�{���́A�u�͂��߂Ɂv�u�����Ɋāv����u�����Ɂv�Ɏ���܂Ŋe�E14���̕��X�̓Ď��ȕ��͂ō\������Ă��B������������I�ɂȂ邪�nj����L���Ă݂����B
�u�͂��߂Ɂv�͎O�D�B���{��c��ɂ����̂����V��I�Ȉ��A���ł͂Ȃ��B���̖`�����Łu�c���������ł����ӂ̔O����������ƍl���āc�v�]�X�ƁA�e�E�̐l�B�ƌ����āu�V�c�É��䑦��20�N��j�ψ���v���ݗ����ꂽ���Ƃ��L����Ă��B�u���ӂ̔O�v�̘Z���������̖ڂɏĂ������B��j�A�c��A���j�Г��X�̕����Ђ͑��ł��ڂɂ��邪�A���ӂ̔O���������`�ł���Ǝv�ӂ���ł���B
�u�͂��߂Ɂv�ɂ́u�É��ƍ��������ԐM���ƌh���̕R�сv�Ƃ̕��肪�t�����Ă�āA���a�V�c�̏I�펞�̂���A�䏢�͐Y����b��ꡂ��C�݂̑��������ԁu���Ȃ��i�v�A����É��̔�Вn�ւ̂������Ђ�ԗ�̍s�K�ɐG��Ă��B�u�����Ɋāv�̓����X�L�c���i��j�c���A�����b�l��\�j���A�É��Ƒ�w�����Ƃ̂��ƂŊԋ߂Ŕq�����̌��Ȃǂ���钆�ŁA�{�����s�̈Ӌ`���q�ׂ��Ă��B
�u���� �c���Ɠ��{�l�v�ł́A�`���́u���{�l�ɂƂ��Ă̓V�c�v�Ƒ肷�钆���P�������̍c���_�͗��j�I�ȕ����_�Ȏ��_����c���`���̈Ӌ`���~�X���������̂ŁA�K�ǂ��ׂ����̂Ƌ����������������B���̕������v�c���́u����@�g�́w���{�c���_�x-�u���R�����`�̒Z���v�u�s���̌��E�v�Ɓu�c���̖����v�v���A�ߑ�I�@�����ƂȂ�������ƍ���������c���̖����̏d�v����������Ă��B
���������c���́u�����̈��J���F��c���̓`��-�{���́u�V���Ձv�ɎQ���Ă��������āv�ł́A���t���[�������Ƃ��ĎQ���V���Ղ��u���ꂾ���̗�I�ȃG�l���M�[���������̂͏��߂āc�v�ƐU��Ԃ�u���{���̍Վ�v�ł��邨����Ɍ��y���Ă�B
�����c����c���́u���a�V�c�Ɓw���a�̓��x-�c����g�߂Ɋ�����܂��Â���̃��f���v�ł́A�u��˂̒��E�����q�v�I�o�c���Ȃ�ł͂̂��̂ŁA�����q�s�E�˓�����ł́u���a�̓��v����L�O�s���i�����\��N�B�����Q���������j�����߁A�������̏d���}�b���Љ��Ă��B
�����u�ے��V�c�l-�w�J���ꂽ�c���x�_�̌��v�i�匴�N�j�����j�ł͐��I�ȋ���������ے��̖{���I��ӂ��A�u�܉ӏ��̌䐾���Ɩ����V�c-�ߑ㍑�Ƃ̗��O�ƍ\�z�v�i��{���ۋ����j�ł͕��Ñ��ېV�̓��{�I���O�̈Ӗ����Ђ��A�u���{�͓V�c�̋F��Ɍ���Ă���v�i���Y���C�����j�ł͕É��̌�{���̖{�����A���ꂼ����I�Ȍ����܂ւȌ��ɔM��������Ă��B
�u���� ����V�c�����v�ł́A����É��ɂ��Ă̋�̓I�ȋL�q�ł����āA����ɐS�ɔ�����̂��������B�����̊W�Ń^�C�g���݂̂��L����B
�u����É��́w����ŊJ�x�̋F��-�T�R��c�A�F���V�c�A�����č���É��̐ΐ����s�K�v�i�ΐ��������{�E�c�������{�i�j�A�u��Â̕����Ɩ����_��-���ƂƂ��Ẳ߂���s���߂����Âɐ��������c���v�i���{���ېN��������E��������j�A�u�V�c�c�@���É��̂�����-�w��Вn���������x�w�ԗ�̗��x�w�O�����K��x�v�i���{��c�E�����L�O���������j�A�u�c���̓`�����p�����V�c�É�-��́E���̐��Ƃ����t���̒��Łv�i���{��c�E�]�蓹�N��C�������j�B
�ǂ̕���q�ǂ��Ă��A���c�������U�Ȃ����S�̉��ɍ����̓��{���Ƃ̓������ۂ���Ă��Ƃ̊������߂ċ��������B�}�炸���u�É��̌�S��m��w�͂��c�v�Ƃ̉��t��v���Y�搶�̂����t���S���Ă����B
�u�����Ɂv�i���{��c�o�ϐl���u��E�F�s�{�c�F��j���܂��̌��I�ȓ��e�ŁA��z�{�a���Ƃ̂����ہA�g���R�v�����́u�����v���z�E���l�s���断������̌N���㎛�̗R���Ȃǂ��q�ׂ��Ă��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�R�������j
��54��S���w���N���h�����@���i�_�ސ쌧�j�ɂĊJ�ÁI
���J��@�O��q�搶
�y�}�E�M�����|�搶
-
��l�͂ǂ������ė����̂���X�͂ǂ�������ׂ��Ȃ̂�-
�����F8��20���i�j�`23���i���j
�ꏊ�F���؎s�����R�ӂꂠ���Z���^�[
�Q����F�w�� 20,000�~�@�Љ�l 35,000�~
���� ��53�h�����̋L�^�W
�w���{�ւ̉�A ��44�W�x���s�I
�艿900�~ ����210�~
�ҏW��L
�ŋ߂����Ŏ��ɂ����^�]�_�Ƃ́u���Z�ȕÉ��ł͂��邪���j��N�w�ɂ����Ƃ��S���c�v�]�X�̃X�s�[�`�ɂ͋��������B�{�Łu�V���Љ�v���Ђ́u��2�́v�ŒԂ��Ă��u�ΐ����s�K�v�u�ԗ�̗��v���X�̂ق�̈�[�ł��A�����F�����Ă�Ƃ�����c�B����É��̂��̂̈����ǂ�ł�Ȃ��Ƃ��ӂ��ƂȂ̂��炤���B�����Ԉ�Ђ��ƈ�u�킪�����^�����B
�i�R���j