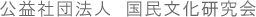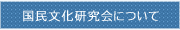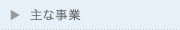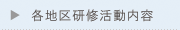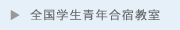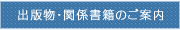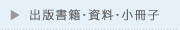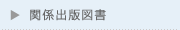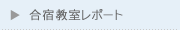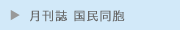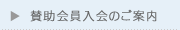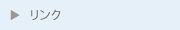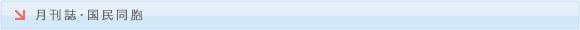
第663号
| 執筆者 | 題名 |
| 工藤 千代子 | 憲法改正の署名活動の中で思ったこと - 「先人の魂」が脈打つ古典を読むことの大切さ - |
| 山内 健生 | いま改めて仰ぐ太子外交 - 「冀(ねがは)くは大国惟新の化を聞かん」 - |
| 古賀 智 | 当用漢字制定によって失はれたもの(下) - 漢字の書き換へを難ず - |
| 布瀬 雅義 | 韓国併合」をどう見るか(下) - 問題あり! 中学校歴史教科書の現状 - |
| 新刊紹介 江崎道朗著 PHP新書 『コミンテルンの謀略と日本の敗戦』 税別980円 |
忘れもしない昨春平成28年4月13日のこと。ふだん乗り降りしてゐる東海道線の藤沢駅前で憲法改正の署名を求める街宣を数名の仲間と始めようとした時であった。「九条の会」の百人ほどに取り囲まれた。彼らは広場を埋め尽し「九条を壊すな」「安倍を許すな」「子供達を戦場に送るな」などと連呼して、私達の声をかき消した。私達の街宣を知ったTBS(東京放送)と神奈川新聞が「九条の会」に情報を拡げて仕掛けたものだった。翌日の神奈川新聞には「街中でふってわいた憲法論議」との記事が載ってゐた。なぜその場で記者やカメラマンが待機してゐたのか。マスコミの偏向とその横暴ぶりには今更ながら腹立たしかった。
その時気付いたことがある。安倍政権に対して「独裁」とか「ヒットラー」とかと的外れなことが何故言へるのか。「言論の自由」を謳ひながら、彼らは他者の立場を頭から否定する。もしこの人達が支持する政権が出現すれば、中国政府のやうに〝反対派〟を徹底的に押さへつけるに違ひない。自らが権力者になった時のことを想ひ描くからこその言動ではないかと思ったのである。
私の住む神奈川県は左翼勢が強く地元紙の偏向もあって「第二の沖縄」と言ひたいくらゐである。ここで「負けてはならぬ」といふ思ひから、毎月街宣を続けて、10月で17回となった。ある日、街宣を終りかけた時、「署名します。僕空自のパイロットだったのです」といふ男性が現れた。「私の息子は陸自です。空自は平時有事問はず大変ですよね」と私は応じた。「頑張ってくださいね」と握手を求められたが、自衛官とその家族との間に伝はる得も言へぬ交流だった。「改憲は自衛官の総意である」と改めて感じたことだった。
マスコミの一面的報道に力を得て、左翼は「改憲すると戦争につながる」、「改憲すると自衛官が辞めてしまって徴兵制が導入される」などと国民の不安を煽ってゐる。そのため「憲法改正→戦争」といった思考停止の単純極まりない見方が依然として根強い。憲法は私達の為にあるものであって、憲法の為に私達がある訳ではない。もはや、野党と共闘するマスコミの倒閣運動となってゐる。この政治闘争には、短・中期的視野からの対策―偏向報道の実態を広く世間に知らしめること(これも容易なことではないが)―が不可欠であることは言ふまでもないが、一方で、真に日本人としての自覚を呼び覚ます息の長い努力も必要だと思ふ。
私は国文研の合宿教室で知識の多寡とは異なる「学問と人生」に取り組む姿勢を先生方から学んだ。そこでは日本人の情感から来る深い友情の世界の大切さが説かれてゐた。左派の人達の間にも友情はあるだらうが、その根柢には先人の歩みを冷視して国家を巨悪視する憎しみの感情があるやうに思はれる。それは日本人の情感とは大きくかけ離れたものと言ふ他はない。
近頃ことに、先人の魂が脈打つ古典を読むことの大切さを痛感してゐる。かつて合宿教室で、小柳陽太郎先生が寺田虎彦の言葉を紹介された。「万葉集は読めば読むほど面白き本、国民みな此れを読めば思想問題など起るまじく候」と。父祖の遺した言葉を手に取って、味はひ大切に扱っていく。さうした心持ちに徹したら、思想問題など氷解するはずである、といふことだらう。万葉集のほかにも、古事記、明治天皇御集、黒上正一郎先生の『聖徳太子の信仰思想と日本文化創業』、戦中学徒遺詠遺文集『いのちささげて』(国文研叢書)等々、書棚に並ぶ書物を改めて味読したいと思ふ。
下記は明治天皇の「落葉有聲」(明治39年) といふ御製である。
なかなかに風のたえたる夜はにこそおつる木(こ)の葉の音はきこゆれ
風がぱたっと途絶えた深夜(夜半(よは))、さうした折こそ木の葉の落ちる音がはっきりと聞えてくる。葉の一枚が落ちる僅かな音をも聞き逃されない。心に滲みるお歌である。
悲しいかな、今も、飢ゑた国民をよそに核開発を強行する独裁国がある。我が国は落葉一枚のかすかな命にもお耳を傾けられる天皇を頂いてきた。戦後、古典は軽んじられてゐるが、古典を読むことは日本人として生れた命の根源に触れることだ。その世界へ一人でも多くの人を誘ふべく努めたいと思ってゐる。
(元、コピーライター 主婦)
はじめに
今日まで続く「十七条憲法の命脈」
聖徳太子は推古天皇の摂政として一大国内改革に挺身した国史上、傑出した偉人であるが、その業績は内治外交の所謂「政治」の領域から、『古事記』『日本書紀』の原史料とも言はれる『天皇記』『国記』の編纂、「人心の有り様」を見定めた仏典研究「三経義疏」に至るまで多岐多様なものがある。
ことに、「道徳政治の理想と統一国家の理念」(協心協力の公的精神)を説いた「十七条憲法」(推古天皇12年、604)は、〝人間性への深い洞察〟に基づくもので、単なる政治文書ではなく1400年後の今日なほ指導者はもとより国民各層の老若男女のそれぞれの立場からも範として仰ぐべきものと思ってゐる。それは直接的には「官吏の心得」を示したものではあったが、普遍的な確かな視線によるものだから、時代や年齢の差異を超えて読む者の心に響くものを内包してゐる。現在のわが国の政治と世相の乱れは「十七条憲法」を忘れたところに起因してゐると言っても言ひ過ぎではないと思ふほどである。
本稿では太子の業績と目される対隋自主外交の展開、「遣隋使」について拙考を述べようとすものだが、その前に少しだけ「十七条憲法」がどう読まれたかについて概略ふり返ってみたい。
「十七条憲法」は、制定200余年後の弘仁11年(820)頃に編纂された律令の追加法令集「弘仁格式」の序に〝国家の制法、茲(ここ)より始まる〟とあるやうに、国法の初めとして位置づけられてゐるが、平安時代はもとより鎌倉以降の武家政治の時代にあっても、法令の拠りどころとして一部の文言が引かれてゐる。これらは形式的なもので「十七条憲法」の本旨からは離れてはゐたが、戦国時代の分国法(戦国家法)や千年後の江戸幕府の大名統制法(「武家諸法度」元和元年、1615)の中にも、「十七条憲法」の一節が摘み喰ひながらも引用されてゐるのだ。
「十七条憲法」が示した「協心協力の公的精神」が全的に甦るのは、花山信勝氏(東大名誉教授、故人)が『聖徳太子と憲法十七条』で説かれたやうに、慶応4年・明治元年(1868)の公論尊重を謳ふ「五箇条の御誓文」によってであった。
「一、広く会議を興し、万機公論に決すべし」から始まる御誓文は明治新政の根本方針を示したもので、それをさらに近代的な立憲国家に相応しく法文的に整へたものが明治22年の帝国憲法であった。憲法発布の翌年には第一回の衆議院議員選挙が実施され、帝国議会が発足してゐる。明治初年以来、自由民権派によって広く展開された国会開設要求の拠りどころとされたのも公論尊重を謳ふ「五箇条の御誓文」であった。
さすれば昭和天皇が、ポツダム宣言受諾後、初めて迎へた昭和21年元旦に発せられた「新日本建設に関する詔書」の冒頭に「五箇条の御誓文」全五条を掲げられ、「叡旨公明正大、また何をか加へん」とされてゐる事実は、ことのほか重大な意味を持つものと思ふのである。そこに私は「十七条憲法」に発して昭和・平成の御代にまで至る連綿たる国史の命脈を仰ぐのである。
本稿では、その「十七条憲法」についての論述は他日に譲るとして、それと並ぶ太子の業績と目される自主外交の展開、即ち「遣隋使の派遣」について、屋上屋を重ねるきらいがあるが、拙見を記してみたい。
「倭・倭国」から「日本・日本国」へ
遣隋使といへば何をさて措いても小野(をのの)妹子(いもこ)が携行した国書の存在である。即ち推古天皇15年、隋煬帝(ようだい)の大業3年(607)、「これを覧(み)て悦ばず…、蛮夷(倭国)の書、無礼なる者有り。復(また)以て聞(ぶん)する勿れ」と煬帝に言はしめた「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙無(つつがな)きや」云々といふ『隋書』東夷伝「倭国」の条が伝へる国書である。
天の命を承けた唯一の天下の主(あるじ)たる天子に向って「天子」を名乗るとは無学な礼儀知らずめ、以後、取り次ぐことはないと煬帝は怒ってはみたものの、やはり気になったのだらう、小野妹子の帰国に際し裴世清(はい せい せい)を随行させて倭国の実情を探らせてゐる。シナ統一王朝たる隋皇帝に対して「天子」から天子へと当時としては異例な呼び掛けに、二度と取り次ぐなとは言ったが、高句麗遠征を企図してゐた煬帝は日本を無視することはできなかったのだらう。
その「大唐(もろこし)の客(まらうと)」裴世清に向って倭王はまた「冀(ねがは)くは大国惟新の化を聞かんことを」と問うてゐる。貴国は見違へるやうに全てが一新したといふことだが、その要諦を知りたいものだ、わが国の参考にもならうから聞かせて欲しいの意とならう。
右の「冀(ねがは)くは大国惟新の化を聞かんことを」との箇所も『隋書』からの引用である(倭王の近くには太子がをられたことだらう)。この遣隋使の派遣を以て、シナ皇帝の冊封秩序から離れて大陸との対等の関係に入ったとされるのも宜(むべ)なるかなである。この問に対して同書によれば裴世清は「わが帝は二儀(天・地)に並ぶ御存在で、その恩恵は広く四海(天下)に及んでゐる。倭王がその徳化を仰いでゐることをお知りになって、かうして私を派遣したのだ」と尊大に答へてゐる。しかし、わが国についての呼称は『隋書』(7世紀中頃成立)までは「倭」もしくは「倭国」だったが、『旧唐(く とう)書(じよ)』(10世紀中頃成立)では「倭国・日本」となり、『新唐書』(11世紀後半成立)以降は「日本・日本国」となるのである。
ちなみに「倭」の字義に関して、上田万年他編『大字典』を見たら、「倭は支那人の附せし名、…倭は矮(わい)の義なるべし」とあって、「矮は背の低きこと」などとあった(「委は従順にして随ふ」様子をさす)。いふまでもなく、好字(嘉字)ではなく東夷・南蛮・西戎・北狄の中華思想からの呼称であった。
裴世清の帰途に同道して翌推古天皇16年(608)九月、再び隋に使(つかひ)した小野妹子が携へた書状には「東(やまと)の天皇(すめらみこと)、敬みて西(もろこし)の皇帝(き み)に白す」と記されてゐて、その内容は「…… 季秋(このごろ) 薄(やうやく)に冷(すず)し。尊(かしこどころ)、如何に。想ふに清(おだ)(ひか)にか。此は即ち常の如し」云々(『日本書紀』)といふ対等の名に恥ざる堂々たるものだった。
「日出づる処」「日没する処」
「日出づる処の天子」云々の国書は小気味良く、最近も「煬帝は、どうやら隋の〝日の沈むところ〟が〝日の昇るところ〟よりは、劣ったところ、と取ったらしいのです。それでは怒るはずでしょう」云々との文面を目にした(日本の息吹、10月号)。しかし「日出づる処」「日没する処」とは巧みな表記だが、前述したやうに二つとない「天子」の称号を倭王が名乗ったからであって、そこには必ずしも優劣区別の考へはない。
東野治之氏(奈良大学名誉教授)の近刊『聖徳太子―ほんとうの姿を求めて―』(岩波ジュニア新書)によれば、これは大乗経典『摩訶般若波羅蜜経』の注釈書『大智度論』にある東方・西方・南方・北方を「日出づる処」「日没する処」「日行く処」「日行か不(ざ)る処」と譬喩する表記を借りたものといふ。煬帝も仏教に傾倒してゐて菩薩戒を授かるほどだったから、「日出づる処」「日没する処」の表記が『大智度論』からの借用であることはお見通しで、「倭人もなかなか隅に置けないと思ったはず」で、煬帝の怒りは「全世界に一人しかいないはずの〝天子〟を東方の野蛮人の国である倭の君主が名乗った点にあったと見るべきです」(この東野氏の著書は近年の謬説と趣を異にしてゐてご一読をお薦めしたい)。
「返書」喪失の妹子を不問にす
ところで一度目の入隋を果して裴世清を伴ひ帰朝した小野妹子が次のやうに奏上したといふ『日本書紀』の記事は何を物語ってゐるのだらうか。
| 「…唐(もろこし)の帝(きみ)、書を以て臣に授く。然るに百済国を経過(ふ)る日に、百済人、探りて掠(かす)み取る。是(ここ)を以て上(たてまつ)ること得ず」 |
煬帝からの返書を途中の百済で奪はれたといふのである。当然のことながら、群臣たちは合議して、使節たる者は死しても使命を全うすべきが返書を失ふとは何たる怠慢かと、妹子を流罪に処すべしとした。ところが、天皇は「妹子、書を失ふ罪有りと雖も、輙(たやす)く罪すべからず、其(か)の大国(もろこし)の客等(まらうとたち)聞かむこと、亦不良(さがな)し」と仰有って「乃(すなは)ち赦して坐(つみ)したまはず」。
異国に派遣された使節が何よりも大事な返書を帰国の途次、亡失してしまったといふのは如何にも重大なる失態である。群臣たちの流罪にすべしとの奏上は至極当然な対処であるが、それを請けた天皇が「(その通りではあらうが)其の大国の客等聞かむこと、亦不良し」されたのは、もっと高いお立場から推移を見てをられたからであらうし、ここに摂政として太子が関ったであらうことも容易に察せられるところである。
妹子は、返書喪失の責めを問はれなかったばかりか、失脚することなく再び遣はされたといふのだから、背後に何かがあったのではないかとつい想像してみたくもなる。この点に関しては、煬帝からの書状の内容を憚(はばか)った妹子が途中で掠め取られたことにしたのではないかと以前から指摘されてゐる。もしさうだとすると、そのまま奏呈しては差し障りがあるとされた返書の内容を承知の上で、「東の天皇、敬みて西の皇帝に白す」の新しい国書が書かれたことになる。「天子」の呼称を巧みに避けて、再度同趣旨の内容を申達したことになる。(以下次号に続く)
(元拓殖大学日本文化研究所客員教授)
先月号では戦後の国語改革によって制定された当用漢字表・音訓表・字体表がもたらした国語表記上の問題点を述べた。今月号では特に漢字の書き換への問題を取り上げて、その実態を明らかにするとともに、書き換へがもたらしたところの思考・思想への影響を述べる。
漢字書き換への経緯
漢字の書き換へについては、昭和27年4月に政府から各官庁に通達・依命された「公文書作成の要領」の中に次のやうに書かれてゐた。
「当用漢字表・同音訓表で書き表わせないものは、(中略)当用漢字表中の、音が同じで、意味の似た漢字で書きかえる。たとえば
車輌(×)→車両、煽(×)動→扇動、碇(×)泊→停泊、編輯(×)→編集、哺(×)育→保育、抛(×)棄→放棄、傭(×)人→用人、聨(×)合→連合、煉(×)乳→練乳」(仮名遣、×印ママ)
これは公用文を対象にしたものであったが、現実の社会では様々な書き換へが行はれてゐて混乱も生じてゐたために、昭和31年7月5日に国語審議会は「同音の漢字による書きかえ(ママ)」といふ報告書を文部大臣に提出した。
この報告書には「当用漢字の使用を円滑にするため、当用漢字表以外の漢字を含んで構成されている漢語を処理する方法の一つとして、表中同音の別の漢字に書きかえることが考えられる。ここには、その書きかえが妥当であると認め、広く社会に用いられることを希望するものを示した」(仮名遣ママ)として、漢字熟語を中心に341の書き換へ語が示されてゐた。
これは公布される事は無かったのであるが、日本新聞協会が独自に取り決めた数多くの書き換へ語とともに社会全体に広まった。そして、これらの書き換へ語の殆どが正しい漢字語として疑問を持たれる事も無しに日常の国民生活の中に定着して今日に到ってゐる。
漢字書き換への問題点
「同音の漢字による書きかえ」に示された書き換へ語を観察すると様々な問題点が見えてくる。書き換へ語の先頭に示された「愛慾→愛欲」の「慾」を中心に見てみよう。
「慾」については別項で「慾→欲」と示されてゐて、これは「慾」を使ふ熟語の中の「慾」はすべて「欲」に書き換へよといふ意味である。報告書の文中にある「1(ママ)字のものは、左の字は右の字に書きかえ(ママ)てさしつかえ(ママ)ないことを示す」がこれである。「慾」を「欲」に書き換へるものとして「愛慾」の他に「強慾」「色慾」「食慾」「性慾」「大慾」「物慾」「無慾」「名誉慾」が示されてゐた。
しかし、良く考へてみると「慾」は「欲しがる気持ち」といふ意味の名詞であって、書き換へ前の熟語ではその意味で使はれてゐた。それに対して「欲」は「ほっする」といふ意味の動詞として使はれる。
「愛慾→愛欲」「食慾→食欲」については、「愛」「食」に動詞としての用法もあるので、書き換へ後の「愛欲」「食欲」は漢語として、それぞれ「いとしみほっす」「くらひほっす」と訓読する動詞熟語に変ったやうに見える。しかし、現実には書き換へ前と同様に名詞熟語として使ってゐるのだから、動詞の「欲」の意味を拡大して、名詞の「慾」の意味をその中に含めたと解釈しなければならないやうだ。
「色慾→色欲」「性慾→性欲」「物慾→物欲」については、「色」「性」「物」が名詞であるから、「欲」を動詞と考へるといづれも漢語としての訓読が出来なくなったやうに見える。これらも名詞の「慾」の意味を動詞の「欲」の中に含めたと解釈するべきであらう。
「強慾→強欲」「大慾→大欲」については、形容詞の「強」「大」が書き換へ後には、副詞の「しひて」「おほいに」に変化したやうに見える。しかし、現実には書き換へ後も名詞熟語として使ってゐるのだから、同様に「欲」の意味の拡大であらう。
このやうに「同音の漢字による書きかえ」では使はれる漢字の意味までをも改変する事になった。しかし、筆者の手許にある昭和十六年の漢和辞典には、「愛慾」「愛欲」「食慾」「食欲」のいづれもが名詞熟語として記載されてゐるし、同じ構造の「貪慾」については、尾崎紅葉の「金色夜叉」(明治36年)に「貪欲」が使はれてゐるから、「慾→欲」の書き換へが誤りであるとは言ひ切れない。だが、漢字の使ひ分けをきちんとしようとする立場から見れば考へ込まざるを得ない問題点である。
そもそも、漢字にはそれぞれに固有の「形」と「音」と「義」とがあって使ひ分けられてゐたのだが、当用漢字表の制限によって一つの漢字に複数の漢字の義(意味)を持たせようといふのであるから、無理が生じるのは当然の事である。漢字の書き換へによって元の熟語と全く同じ意味の熟語を作る事は困難な事であって、漢字本来の義を知る者にとっては大変に迷惑な事であった。
ここでは「慾→欲」の書き換への例しか紹介出来なかったが、他の例の一つ一つを吟味すれば、それらの殆どに問題がある。例へば「暗翳→暗影」「暗誦→暗唱」「掩護→援護」「根柢→根底」「戦歿→戦没」などの書き換へには疑問を感じる。
要するに、漢字一文字づつの意味を深く考へずに、大雑把な使ひ方をせよといふ事なのである。この事は当時の国語政策担当者の国語に対する感性の無さを充分に証明してゐる。また、これらの書き換へ語を受け容れた国民の国語に対する感性もどうかしてゐたのであらう。
「慰藉料→慰謝料」の問題点
「同音の漢字による書きかえ」には「慰藉料」を「慰謝料」に書き換へよとある。この書き換へは戦後の思考・思想に最も悪影響を与へたものの一つであると筆者は考へる。
「藉」には「人の気持ちを落ち着かせたり、やはらげたり、なぐさめたり」といふ意味がある。熟語の「慰藉」は「なぐさめたすける・なぐさめいたはる」といふ意味を表はすのであるが、「藉」を「わびる・あやまる」といふ意味を持つ「謝」に書き換へたために、「謝罪」の意味が加はった。しかも法律用語の「慰謝料」としてしか使はれない言葉になったために、本来の「なぐさめたすける・なぐさめいたはる」の意味は薄れて、「謝罪」の意味だけが強調されるやうになった。
近年の報道を見てゐると、何か事件が起るとすぐに「謝罪しろ、頭を下げろ、賠償しろ、慰謝料を払へ」などといふ事例が目立つやうになった。そして頭を下げさせ、或いは土下坐までさせた写真やら映像やらを新聞・テレビ・インターネットなどを使って大衆の前に曝すのである。大衆もそれを見て快感を覚えるらしい。これは最早、人民裁判による集団リンチである。このやうにして手に入れた「慰謝料」が「なぐさめ金・いたはり金」であるはずがない。そこで「慰謝料を取られた」といふ言葉も出て来るのである。そこには同胞として互ひになぐさめ合ひ、いたはり合って生きて行かうといふ気持は無い。大人の世界がかうなのだから、子供の世界から「いぢめ」が無くなるはずが無い。
いつからこの様な情けない国民に成り下がってしまったのかを考へると、その原因のすべてではないが、「慰藉」を「慰謝」に書き換へて、法律用語の「慰謝料」といふ言葉を作り出した時に始まるのではないかと思ふのである。
智慧と感性
「同音の漢字による書きかえ」には「智慧」を「知恵」に書き換へよとある。この書き換へこそが現代社会の思考・思想を浅薄にした最大の原因であると筆者は考へる。「智→知」ともあるから「智」をすべて捨て去れといふ意味である。だが「知」の義の中に「智」の義を含める事が出来るのだらうか。
知覚によって認知した知識の塊に、自らの主観に基づく責任ある思考を能動的かつ斃而後已(たふ れて のち やむ)の覚悟で一所懸命に加へても、得られるかどうかが分らぬものが「智」なのではないだらうか。「智」とは本来それほどに奥深いものであって、宇宙のやうに宏大無辺のものである。その宇宙の果に近い人を「智者」といひ、その人の「ちゑ」を「智慧」といふのであらう。したがって「知」の義をいくら拡大しても「智」をその中に含める事は出来ない。
「慧」も「智」と同じく「さとし・かしこし」の意味であって、「ちゑ」を表はす。この二文字を重ねて「智慧」とも「慧智」ともいふ。「慧眼」「慧悟」といふ言葉もある。
これに対して、「恵」は「めぐむ・めぐみ」の意味が強くて、「知恵」は「知識のめぐみ」としか読めない。「ちゑ」は漢字で「知恵」と書くと教へられた人たちが「知識」を「ちゑ」だと誤解しても不思議ではない。筆者は「智慧→知恵」の書き換へは誤りであると考へる。
この「智慧」は「智者」の独占物ではない。人間は生れながらにして内なる宇宙に「智慧」を有してゐて、健全な「感性」によって「智慧」が現れて生き生きとした精神生活を送れるのである。だが、現実生活の中で次第に怠惰になって「感性」は鈍り「智慧」も失はれて行く。
かうした怠惰な大衆に対して、マスコミやジャーナリズムは恣意的或いは意図的に選択・加工した情報を一方的に送り附ける。大衆は大量の情報を「知識」として取り入れるのに精一杯で、自らの「智慧」と「感性」とを働かせてそれらの情報の真偽を識別して判断を下す事が出来なくなってゐるやうに見える。
かうした現状であるから、漢字の書き換へによって失はれた「智慧」を取り戻さなければならない。国語だけではなく、国史・国憲・国防といふ凡そ「国」の字の附くものに対しては、与へられた「知識」に満足するのではなく、自らの「智慧」と「感性」とによる能動的かつ主体的な思考を働かせて、真正なる国家とは何かを考へて行動したいものである。
(元 富士通(株))
対日協力をした「一進会」100万人
日露戦争初期に朝鮮北部を旅して『朝鮮の悲劇』を書いたカナダ人記者F・A・マッケンジーは「どこでも韓国の国民からは日本軍に対する友好的話題ばかりを聞かされた。労務者や農民達も友好的であった」と書いてゐる。さらに「下層階級の人々は、日本が自国の地方官僚の圧政を正してくれるやうにと希望してゐたし、上流階級の人々の多くは、朝鮮の遠大な改革は外国の援助なしには遂行し難いと確信してをり、そのため日本に心を寄せてゐた」旨を記してゐる。
その「日本に心を寄せてゐた」人々の集まりが「一進会」で、当時会員数、百万、韓国最大の政党と言はれた。日露戦争当初、朝鮮鉄道は釜山から京城(ソウル)までしかなく、日本陸軍は満州に武器弾薬を輸送するのに困窮してゐた。これを助けるべく、15万人もの一進会会員が手弁当で鉄道敷設工事に参加した。また物資運搬を助けた会員も11万5千人もゐたといふ。
1907年から日韓併合翌年の1911年までに日本軍と戦った「義兵」は14万人を超えると言はれてゐるが、その二倍近い人達が日露戦争時(1904~5)には、日本に協力してゐるのである。抗日「義兵運動」を書くなら、かうした対日協力の事実も書かなくては適正な教科書とは言へない。教科書検定はどうなってゐるのだらうか。
「韓国併合に関する条約」は違法か?
明治42年(1909)、一進会は「我が国の皇帝陛下と日本天皇陛下に懇願し、朝鮮人も日本人と同じ一等国民の待遇を享受して、政府と社会を発展させようではないか」との声明を発した。
これを受ける形で、翌明治43年8月22日、「韓国併合に関する条約」に寺内正毅・韓国統監と李完用総理が調印し、29日には大韓帝国皇帝が勅諭を公布して成立させてゐる。
近年、この条約の違法性を国際社会に認めさせようと、韓国側の強い働き掛けで「韓国併合再検討国際会議」が三回も開かれた。韓国側の主張は「武力で強制された」「条約に国王の署名がない」などを根拠にしたものだったが、いづれも英国の学者らから反論された。
「武力で強制されたから無効」などと言ったら、戦争後に勝者と敗者の結ぶ講和条約はすべて無効となる(戦後、日本が結んだサンフランシスコ講和条約を想起すべきだ)。「国王の署名がないから無効」と言ったら、国家元首が署名しない条約はすべて無効となってしまう。併合条約は当時の首相が全権大使として皇帝の代りに署名してゐるのだ。
世界的には『韓国併合ニ関スル条約』は当時の国際法上合法であるとするのが多数派であり、違法論は現在では、韓国と北朝鮮以外では少数派である。しかし油断は禁物である。
歴史学者や国際法学者の間のやり取りのことだと思ふことなく、外務省にはしっかりと情報を蒐集して、適宜に反論するやうに願ひたい。
歴史教科書は両面を正しく記述すべきだ
また、国際法の権威ジェームズ・クロフォード・ケンブリッジ大学教授は、当時の国際慣行法からすると英米を始めとする列強に「認められてゐる」以上、仮に手続きにどのやうに大きな瑕疵があらうとも「無効」といふことはできない、と指摘してゐる。当時、英米は「認める」どころか、韓国併合を日本に勧めたのである。日露戦争のポーツマス講和会議のあとで、ルーズベルト大統領は小村全権代表に、「将来の禍根を絶滅させるには保護化あるのみ。それが韓国の安寧と東洋平和のため最良の策なるべし」と言ってゐたし、イギリスのランズダウン外務大臣も「英国は日本の対韓措置に異議なきのみならず、却って欣然その成就を希望する」とまで言ひ切った。
英米の後押しは、韓国の変転極まりない事大主義が、日清戦争、日露戦争を誘発したからである。その意見が正しかったことは、日本統治が始まってから大東亜戦争敗戦までの朝鮮半島は、35年間の平和と繁栄の時代を迎へた事で証明されてゐる。
韓国併合といふ大きな政治的事件には、当然、賛成派も反対派もゐた。マイナス面もプラス面もあった。歴史教科書としてはその両面を公正に記述すべきである。
日本統治時代の鉄道・道路・港湾・発電(電気)等の基盤整備に加へて教育の普及や食糧増産などを抜きにしては、今日の韓国を語ることは到底不可能だからである。
付・数字が語る日韓併合時代 李朝時代の飢餓からの脱出
北朝鮮の悲惨な食糧事情が伝へられるが、李朝時代の朝鮮でも人口はほとんど増加しなかった。1753年の730万人が、100年後の1850年でも、750万人になったに過ぎない。
朝鮮半島が急激な人口増加を迎へるのは、20世紀に入ってからである。1906年(明治39年)からの20年間で、980万人から、1866万人と倍増した。さらに1938年には2400万人となった。日韓併合時代である。
人口急増の原因
この人口増加の原因としては、一つは第6代宇垣一成総督による「農村振興運動」などの民生向上活動である。30年で内地(日本)の生活水準に追ひつくことを目標に、農村植林、水田開拓などの積極的な国土開発による食料の増産が図られた。併合当初、米の生産量が約1千万石であったのが、20年後の昭和に入ると、2千万石へと倍増した。
もう一つは医療制度の確立で、特に伝染病の予防である。日韓併合の1910年から徹底的な検疫を実施し、コレラ、天然痘、ペストなどは、1918年から20年に掛けての大流行を最後に押さへ込まれ、乳児死亡率が激減した。さらにインド、中国から朝鮮にかけて猛威を振るってゐたハンセン病退治のための救ライ事業として、世界的規模と質を誇る小鹿島(そろくと)更正園を作って、6千人以上もの患者を収容してゐる。
李朝時代の飢餓の一因は森林破壊にあった。定住しない焼き畑農民は、山林を焼き払ひ、一定期間耕作すると、他へ移ってしまふ。さらに、冬季の薪(まき)需要のための乱伐。そこに豪雨が来れば、表土は流出して禿げ山となってしまふ。降れば洪水、降らねば干魃(かん ばつ)では、農業生産は崩壊する。治水の前に治山が必要といふのが、寺内初代総督の方針であった。朝鮮総督府は併合の翌1911年からの30年間で、5億9千万本の植林を行った。朝鮮全人口の一人あたり約25本といふ膨大な数である。
植林事業と平行して、洪水予防と灌漑のための全国的な河川事業。内地にもなかった一七万キロワット級のいくつもの巨大水力発電所の建設、15万ヘクタール以上もの砂防工事等々、大規模かつ総合的な国土開発事業が展開された。
これらの結果、水田は明治43年(1910)の84万町歩が、昭和3年(1928)ごろには162万町歩と倍増した。
きめこまかな農民保護政策
大規模な国土開発とともに、きめこまかな民生安定化の施策がとられた。宇垣総督時代には、当時八割を占めた小作農の生活を安定させるため、朝鮮農地令を実施して小作権を確立し、税制を整理して、負担を軽くした。さらに低利資金を融通して高利債務を返還させ、多角農業主義により綿花栽培や山羊飼育を奨励した。
また従来、朝鮮農民が見捨ててゐたやうな不毛の地に入植して、開墾する日系移民も約3800戸あった。これらの移住農民が、米の改良品種、新農法を持ち込み、養豚、養鶏、養蚕などの多角経営を図り、また厳冬にも家族ぐるみで副業に励む姿を見せた。日系農家の自力更正が、朝鮮農民の意識改革に大きな役割を果したのである。
さらに米作保護のために、逆ざやの価格政策がとられた。昭和18年の生産者の手取り価格は生産奨励金なども含めると一石(二俵半、150キロ)62円50銭、消費者価格は43円、この逆ざやは政府が負担してゐた。
農業生産が軌道に乗ると、内地への移出が急増した。併合当時わづか11万石だったのが、昭和3年には670万石までになった。これは内地の農家を圧迫し、政府は朝鮮米の移入制限を図らうとするが、総督府は徹底的にこれに反対して、朝鮮農民を守った。
ちなみに当時の日本人の土地所有は一割程度なので、総督府の農業保護の恩恵の九割は、朝鮮農民が受けたと言へる。また治山治水事業での労働に対しては、作業者に日当が支払はれた。李朝時代にはなかったことである。
開発を支へた資金源は?
宇垣総督時代の総督府予算は昭和5年で約2億円の規模、これに対して朝鮮内部の税収は5千万円程度であった。日本の政府予算(すなはち日本国民の税金)から、毎年一千数100万円から2千万円が補填された。この予算獲得のため、総督府の関係者が帝国議会や大蔵省の説得に奔走したといふから、官僚の世界は今も昔も変らない。不足分は、日本の金融市場から集めた公債によってまかなはれた。
朝鮮総督府の事業は、その他にも教育の普及、工業発展など多方面に及ぶ。その投資は、結果的には、すべて日本からの持ち出しで、大きな負担となってゐた。日韓併合は日本の安全保障が主因だったが、戦後は米ソ冷戦から米国が関与したことで、わが国はその負担からは免れた。
[参考]黄文雄『 歪められた朝鮮総督府』光文社、中村粲『「韓国併合」とは何だったのか』日本政策研究センター、名越二荒之助『日韓2000年の真実』国際企画。
(初出、国際派日本人養成講座第1000 七号及び第56号、一部改稿)
(元、在米日本企業役員)
このほど江崎道朗氏(本会会員)の新著『コミンテルンの謀略と日本の敗戦』がPHP新書から刊行された。旧ソ連が仕掛けた国際共産主義運動組織「コミンテルン」(1919年結成)による謀略が、大正期以降、わが国の各方面に浸食して、先の大戦の敗戦にまでつながった経緯を追究した労作で、共産主義思想の禍々しさを改めて教へてくれる。
著者は、昭和37年(1962)東京に生れ、九州大卒。月刊誌編集や国会議員政策スタッフなどを経て、安全保障やインテリジェンス、近現代史研究に従事。前著『アメリカ側から見た東京裁判史観の虚妄』(祥伝社新書)については、本紙5月号に山本博資氏による紹介がある。
本書は①「ロシア革命とコミンテルンの謀略―戦前の日本もスパイ天国だった」、②「『二つに断裂した日本』と無用な敵を作り出した言論弾圧」、③「日本の軍部に対するコミンテルンの浸透工作」、④「昭和の『国家革新』運動を背後から操ったコミンテルン」、⑤『保守自由主義』vs『右翼全体主義』『左翼全体主義』」、⑥「尾崎・ゾルゲの対日工作と、政府への浸透」の6章から構成されてゐる。
これらの表題からも窺へるやうに、共産主義とはいかなる思想で、レーニンによるロシア共産革命(1917年)の影響がいかに日本に及んだかから説き起し、併せて、その謀略的な実態と、それが浸透する下地ともなった日本の社会的な問題点にも言及してゐる。また、共産主義の一党独裁的な全体主義思想が、左翼勢力ばかりではなく、昭和前期には、5・15事件や2・26事件を招来した国家革新運動や大東亜戦争に向ふ中で高まった「総力戦・統制経済の理念」の底に色濃く流れてゐたことが詳述されてゐる。近衛・東條両内閣の内部で、ゾルゲや尾崎秀実(ほつみ)らコミンテルンのスパイが暗躍して、天皇のご意向に反し支那事変の泥沼化を工作し、日米開戦の流れを作ったことなども説かれてゐる。
共産主義は、土地や工場など生産手段を国有化して、経済的平等を目指す考へ方だ。それは生産手段の私有を前提とする資本主義が、地主と小作人、経営者と労働者といった階級を生じ、貧富の格差を広げてしまふといふ矛盾の解決を探る中で生れた。しかし、実態は共産党の一党独裁による恐怖政治であった。
本書で、なるほどと思ったことは、明治維新以降、日本が近代産業国家の道を進む中で、表面化してきた格差や貧困への問題意識が、エリートたちの正義感を刺激して、彼らを社会主義に惹き付けたといふ指摘である。大正期以降、貧困や労働問題に解決策を提示してゐたのは主に社会主義者やキリスト教徒であって、「保守派の多くは、道徳や家族制度、国防や外交問題のほうに注目し、経済問題の重要さをわかっていなかった」と説く。さらに大正から昭和初期には、貧困・労働問題に取り組み、「民のための政治」を掲げると、政府批判とみなされ、「非国民」のレッテルを張られる風潮もあった。これらが正義感の強い人々を、反体制派に追ひやることになったともいふ。貧困問題や社会改革を訴へようとすると、社会主義の術語と論理で語ることになってしまふといふジレンマもあった。一面の真理を突く鋭い指摘ではあるまいか。
第5章「『保守自由主義』vs『右翼全体主義』『左翼全体主義』」は、本会(国文研)の源流についての記述と言ってもいいほどで、昭和10年代の若き日の小田村寅二郎先生らの日本学生協会グループの思想戦とその意義について述べられてゐる。
長引く支那事変と米国との戦争が近づく近衛・東條内閣の頃、「総力戦・統制経済の考へ方」が強まった。大政翼賛会に象徴されるこれらの動きは、戦後の通念では、「右傾ファッショ化」として理解されがちだが、背景には、当時の革新官僚と呼ばれたエリートを惹き付けてゐた社会主義的発想があり、それに付け込むコミンテルンの赤化工作がうごめいてゐた。その危険性を早々と見抜いて果敢に警鐘を鳴らし続けたのが、小田村先生たちだった。その警鐘の根拠には、大日本帝国憲法に流れる君民共治の国柄を踏まへた理念についての正確な把握があり、議会制民主主義や自由経済を否定しようとする統治や経済運営が、憲法精神からの逸脱になるとの確信があった。小田村先生らの立場を「保守自由主義」と位置づけ、極めて正統的だったと論述されてゐる。
本書から多くを教はったが、ことに国文研の会員にとっては必読の書と思った。
(茨城新聞社 佐川友一)
編集後記
10/22投票の衆院選で与党優勢を伝へる投票日前(10/17)発売の『週刊朝日』に「自+公+希+維 350議席以上の改憲連立政権が誕生へ “安倍大政翼賛会”の悪夢でいいのか」との大見出しが躍ってゐた。「悪夢」にも驚いたが、多党間の合意形成を「大政翼賛会」とは恐れ入ったレッテル貼りだった。やたら棍棒を振り回す北朝鮮を前にして、猶も手足を縛る「第九条」を護持して殉ぜよといふのか。
(山内)